31、大和路-1
左門は迷っていた。
田島主膳が熱田神社を去る日が近づいていて、権宮司の引き継ぎ行事もすでに終わり、主膳の荷物はすでに京の九条家に送られていた。
主膳は熱田神社を去ることに全く未練はない様子だった。主膳にとっては妻子も京にいることだし、御所の南西に位置する広大な九条邸での今後の暮らしは、熱田神社を任されていた時のように経済的なやりくりが必要ないだけに心労は少ないはずだった。
主膳は左門にも救いの手を差し伸べ、京に同行するように言ってくれている。
弥吉は各務原に去り、平三郎も弥吉を手助けすべく、弥吉に断られたにも関わらず、数日を経てから弥吉の後を追って各務原に向かった。
主膳と親しい職員の何人かは進退を共にして退職、あるいは他の神社に迎えられて去ったが、左門だけは迎えてくれる人もなく行く宛もない。したがって、ここで何の目的もなく神社を離れると、その瞬間から路頭に迷うことになる。
か、といって田島主膳の言葉を真に受けて誘いに乗ったら主膳の立場を悪くする。
公家の九条家は田島主膳一人を招いたのであって、左門までは受け入れていない。最初から迷惑をかけたのでは今後の左門の生き方にも支障を来すのは間違いない。
だからといって、保護者の去った熱田神社に残って、新たな権宮司の馬場家にへつらって暮らすのも、人間関係に不器用な左門にはとても出来そうもない。
田島主膳を招いた公家衆の最右翼に位置する九条家については、主膳から聞いて左門もおぼろげには知っていた。
九条家とは、皇室とも縁のあった藤原氏北家から出た藤原兼実を祖として京の九条に屋敷を構えたのが家名の由来だった。本来は平家と密接な関係にあったにも関わらず、平氏と後白河天皇に反旗を翻して源頼朝に接近して関白となり、以後、五摂家を擁立して朝廷内で権勢を振るい、絶えず国政の裏舞台で暗躍してきたとも聞く。
ここに招かれるということは、時あたかも海外からはオランダ、ロシア、イギリス船などが来航し、国内では諸国の飢饉、徒党を組んでの百姓一揆などが、弱体しつつある徳川幕府の屋台骨を揺らしつつあり、時代が九条家の暗躍を求めているのかも知れぬ……
「策士としてのわしの手腕を買ったのかな?」、主膳はこう言って笑った。
京の九条家の当主は、兼実から数えて二十一代目の九条輔嗣(すけつぐ)、その子、尚忠は当代切っての英才で、年齢は左門より二歳ほど下だという。左門は、いつか機会があらば九条尚忠なる若者に会ってみたいと思った。
左門は、会いたい人というところで、ふと過ぎし日のことを想った。
左門が勘当される半年ほど前、萩が白く群れていた秋の午後のことである。
ある日、咲が自室で素読をしていた左門を呼びに来て、父の元に来客があり挨拶に出るようにと言われたことがある。
左門が座に出て、父の上座に座った品のいい武士に挨拶をすると、父が言った。
「こちらは、ご付け家老の成瀬さまじゃ」
付け家老とは、関ヶ原の戦いで天下を統一した徳川家康が新たに築かれた名古屋城に九男の義直を移封したときに、幼少の藩主の後見人として送りこまれた成瀬正成と竹越正信の両家老のことで、いわば幕府の監査役だった。
その両家は、一万石を超えると大名といわれる今、犬山城を守る成瀬家が祿高三万七千石、今尾城の竹越家は三万石で、祿高三千五百石で尾張藩重臣である大道寺家など問題にならないほどの堂々たる勢威を誇っていた。
尾張藩重臣として人望のあった大道寺玄蕃直方は、藩の政りごとには熱心だったが藩内の加熱しがちな政争にはつねに無関心を装って中立の立場を守ってきた。
だが、エゲレス、オロシアなどからの艦船が来航し始めると、夷狄から国を守れという守旧派と開国して新文化を吸収すべしとする進歩派に藩内でも意見が別れて議論百出、それはごく自然に夷狄征伐を主張する武闘派と、国を開き通商を求めよという穏健派の争いにもなり、さらには尾張藩内部の二大勢力の竹越派と成瀬派の二つに割れ、何かにつけて反目し合う切迫した状況になっていた。
こうなると、大道寺家だけは中立を、と常々言っていた玄蕃直方の主張も、時代の波がそれを許さなくなってくる。
大道寺玄蕃は各地各藩の情勢を収集すべく甲賀衆を集め、小間物屋や虚無僧などに形を替えてさまざまな地域に間諜を放ち情報を収集していたのを左門は知っている。ただ、それが尾張藩主の内命を受けてのものか、大道寺家独自のものであったかは左門には知るよしもない。
その集められた情報を分析し、それを父は左門にも語った。政府の外憂への対応は生ぬるく、相模、房総に砲台を設置して外国からの船舶に備えることで、ひとまず外国からの船舶の江戸への接近を阻めるというものだった。しかし、江戸幕府の財政の急場の軍需に放出できるほどの余裕はない。そのために各藩に膨大な拠出金を割り当てるのだが、各藩もまた飢饉や一揆対策で財政は逼迫していて民からのご用金集めに無理難題を押しつけることになる。
とくに、大阪の豪農などには破額の御用金の供出を命じたので、幕府に対しての不平不満が噴出していると聞いた。その不満は、北は津軽藩から南の鹿児島藩内に至るまで広がり、いまや各地の民衆は自分たちを守るべき藩主やそれを束ねる幕府にまで牙を向きはじめようとしていて、いずれの為政者も自藩では結論が出せない問題の火種に抱えて苦慮しているのが現状であることも分かっていた。
左門はこのようなときに、付け家老の成瀬隼人正典に出会ったのだ。
「そちが文武両道に優れた大道寺才次郎か? 噂には聞いていたぞ」
成瀬隼人正典が目を細めて才次郎を見た。口許に笑みはあったが目は鋭かった。
「玄蕃殿はいいお子を持たれた。才次郎は幾歳になられたかな?」
「十八歳にございます」
「そうか、聞くところによると兄じゃは病弱で、大道寺家の世継ぎには次男の才次郎が相応しいとか……」
「あいや、成瀬様。おたわむれは困りますぞ」
「いやいや、これは口性ない世俗の噂じゃて気にされるな。ところで才次郎……」
「はい」
「そちら若者は、天下国家、尾張藩の行く末などをどう見ておられるのじゃ?」
「どう、と言われましても……」
あの時、左門は父の顔を見た。父は苦渋に満ちた顔を隠すように言った。
「思いを存分に述べていいぞ」
そこで左門は「僣越ながら」と断って、日頃、武術の鍛練後に仲間で激して語る夷狄征伐の鎖国武闘論をとうとうと語ると、黙して聞いた成瀬隼人正典が、左門の口が閉じるのを待って重い口調で左門に語りかけた。
「頼もしい限りじゃ。いま、国中がおぬしと同じ意見で沸いている。じゃが、いつ果てるともなく現れる外敵と闘うためには膨大な資金が必要になる。敵は世界……オランダ、ポルトガル、オロシア、エゲレス、スペイン、その何倍もの大国が我が国の富を狙って押し寄せてくるだろう。日本には金と絹が無限にある、そう信じられているらしいのだ」
「そうなると、戦い続けることになります」
「戦って負ければ属国になり、民は奴隷同様の過酷な労働を強いられることになる」
「勝てば?」
「我が国の沿岸で勝ちを収めたとて、所詮は井の中の蛙、相手の国に勝ったのではない。一時的に敵を排除しただけだ。敵は次々に武器を新たにして攻めてくる」
「戦わずに勝つには、いかがなされますか?」
「戦える武力を築いた上で対等の立場で話し合い、国と国の交わりを開く」
「属国にはなりませぬか?」
「民の暮らしが豊かで力があらば属国にはならぬが、民が貧しければ敵になびく」
「それは、どういう意味ですか?」
「人は豊かな暮らしは手放したくなく、お上にも反逆せぬものじゃ」
「成瀬さまは、民を豊かにすることが外敵に勝つことだと……?」
「民はよりよき暮らしを目指すもの。幸せな家族なら死守する気になれる」
「ご家老さまは、本気でそうお考えですか?」
「ほう、本気でないことをここで言うほど暇ではないわ」
「されば、藩が民から搾取して幕府への献金や年貢の取り立てを増やしつつある現状とは異なりませぬか?」
父の玄蕃が見かねて口をはさんだ。
「才次郎、口が過ぎるぞ」
成瀬隼人がそれを制した。
「存分にと申したはずだ。才次郎、思いを言うてみい」
「尾張藩の支配下にはまだ農民一揆の波は来ていませんが、いずれ年貢の取り立てで百姓の暮らしが破綻をきたせば一揆も起こります。今のうちにご三家筆頭の当地だけでも善政を施すべきだと思います」
「よう言うた。だが幕府への軍事用拠出金はいかが致す?」
「聞くところによると、藩主さまは華美を好み、江戸城を真似て名古屋城の大奥に多くの女性を集めて舞や宴に興じられてお過ごしとか、これらを縮小なされるだけで充分かと存じますが……」
成瀬隼人がまじまじと才次郎を見た。細い目が開かれ瞳に鋭さが増している。
「才次郎,おぬしは本当に十八歳か? 玄蕃殿」
「なにか粗相を?」
「いや、大道寺家を長男に継がせたら、この才次郎を成瀬家の養子にくれぬか? きっと尾張藩はおろか、傾きかけた幕府の屋台骨も建て直してくれるやも知れぬぞ」
「もったいない」
「成瀬家にも、才次郎と釣り合いのとれるいい娘がいるでのう」
この最後の言葉が左門の脳裏を刺激して、その後の会話の内容を忘れさせた。
しかし、自分と釣り合いのとれるいい娘……それも、所詮は夢だった。
それでも、いつか再び会ってみたい人……それが成瀬隼人正典だった。
あの時確かに、民の暮らしを豊かにすることがわが国を安泰させる道であることだけは納得できた。民の安住の地、それがあってこそ藩が豊かになり国が栄える。
この、成瀬隼人の言葉を思い出した時、左門は熱田神社を去ることを決意した。これで武士を捨てることになったとしてもいい。今まで世俗にはとんと疎かった左門も、こうして家を出て熱田神社に寄寓し、多少でも世間の荒波に揉まれてみると、自分が育った環境の中で思っていたほど武士の地位が確実なものではないことが理解できた。
どうせ一度は庄内河原で死んだ身だ。民の暮らしに染まってみるのも面白い。

田島主膳が去る朝、左門も旅支度で表に出た。荷はほとんどない身軽な体だった。
「そうか、一緒に行く気になったか……」
「住まいは自分で考えます」
「それもいい。どの地でも野の草、木の実、川に魚がいて飢えることはない」
主膳はそれだけ言うと、手にした編笠を頭に乗せて顎紐を締めながら、鬱蒼と繁る熱田の森の中を多くの関係者の見送りに手を振って、掃き清められた玉石を踏みしめて参道を歩き始めた。その背後を歩く左門の目からなぜか大粒の涙が流れ落ちる。過去の全てを捨てるのが怖いのか、孤独が怖いのか、生きることが怖いのか、なにが悲しいのか左門にはまったく理解できない。ただ訳もなく無性に悲しいのは事実だった。
ゆったりと先を歩く主膳は左門の嗚咽に気づいているのかいないのか、行く末の見えぬ若者の心を案じて胸を傷めているのかいないのか、笠の内で顔が見えぬ田島主膳の表情は窺うべくもない。だが、その主膳の頬を涙のしたたりが濡らしていることに、梢の間越しに洩れる陽光の輝きと熱田の森を吹き抜けるさわやかな風だけは知っていた。
これが左門の熱田への別れと、大和路への第一歩となった。
32、大和路‐2
庄内川の大橋を渡るとき、河原の中央を流れる清流を覗き込みながら主膳が言った。
「どうだ、川の水を飲んでゆくか?」
「水なら、たっぷりありますが」
左門が腰の竹筒を振ると主膳が笑った。
「これが、故郷との今生の別れになるやも知れんからじゃよ」
そう言われると左門も、故郷の水を飲んでおきたい気がする。
「では、権宮司さま、河原に下りましょう」
「もう権宮司ではないぞ」
「されば、田島さま」
「先に行くぞ!」
土手には、すでに彼岸花の群れが真紅の花を秋風に揺らせていた。
主膳は、長い年月の間に多くの人に踏み固められて出来た橋際の階段をゆっくりと下りて河原の大石の上を巧みに歩いて水際まで行き、さっさと腰を折って、流れに手を差し入れて水を掬って旨そうに飲み干している。
左門も真似をして水を飲んだ。熱田からまだいくらも歩いていないのに汗ばんだ体に冷たい水は身体中に染みるほど美味だった。
「ああ、うめえ!」
思わず声を上げると主膳が笑った。
「どうだ、飯も食うか?」
「いま、朝飯を頂いたばかりですが……?」
「今日は、これから忙しくなるからな」

主膳は河原の大石に腰掛けて、背袋から風呂敷包みを取り出し、竹皮で包んだ海苔巻きの握り飯を頬張って口を動かし始めた。こうなると若い左門も我慢が出来ない。
主膳と向かい合うように石に腰掛けて、主膳と同じに用意された握り飯を出して食べ始めた。すると、主膳が口をもぐもぐさせながら言った。
「いま、いくら持ってる?」
「所持金ですか?」
「そうだ」
「父親から勘当されたときの三両に加えて、権宮司さま、いや田島さまから頂いた五両、合わせて八両という大金と小銭が少々あります」
「その五両は三人が腕で稼いだ分の分け前だからどう使おうと自由だが、ご父君から頂いた三両は、生涯けっして手を付けてはならんぞ。いいか、これだけはわしがきつく言い渡しおく」
「かしこまりました。きっと約束いたします」
「では、これから言うことをようく聞け」
「はい」
「道中には、至る所にゴマの蠅という盗人がいて旅人の懐を狙っておる」
「存じております」
「そやつらは、三両以上を懐中に入れた旅人を一目で見抜くそうじゃ」
「なぜ、分かるのですか?」
「人は誰しも懐中に大金があれば、それなりに気持ちがそこに行くものだし、金であれ銀であれ三両となればずっしりした感じで懐に重みが出る。これが分かるらしい」
「田島さまは、まるでゴマの蠅の体験がおありのようですね」
「バカを言うな人聞きの悪い。こんなのは常識だ」
「それで、なにか対策は?」
「一番、たしかなのは背袋に入れて、何気なく扱うことだな」
主膳が清流の川上に顔を向けた。
遠く尾張城の天守閣がかすんで見える。
「この川の上流で才次郎は柳生と戦い、そこから新たな人生が始まった」
「そうでした……」
「人は過去には戻れない。だが、もしも、これがなかったら才次郎は尾張藩の政争に巻き込まれながらも重臣のお家第一で保身の一生を終えたのかも知れんのだぞ」
「そうですね」
「それからみたら、自由の天地で羽ばたける今の境遇は素晴らしいと思わんか?」
「……」
主膳が天を仰ぎ、川を眺めた。
「見ろ、あげヒバリは空に舞って愛を語り、小魚は清流で自由に遊ぶ……しかも、彼らは生きるために餌を求め、外敵から逃れる術も身につけながら成長するのだぞ」
「はい!」
「才次郎は、いまや小魚や小鳥と同じに自由なのだ。自由は素晴らしいが生きるために貪欲でないと、すぐ飢えて死ぬ……先年の飢饉では北陸でも奥羽でも数知れぬ餓死者がでたのを存じておろう」
「聞いております」
「しかも、死者の衣類を剥ぎ、人肉を食む畜生にも劣る者まで出たと聞く」
「すさまじいことですね」
「そこまで飢えていないこの地でも畜生はいるぞ」
「どのような?」
「鈴鹿の山道に入ると白昼でも山賊が出るそうじゃ。彼らは、弱そうな旅人と見るとどこからか現れては脅し、金品を奪い衣類を剥ぎ女を犯し、場合によっては谷底に蹴落とすという凶暴非道な行いで旅人を恐怖に陥れている」
「役人は取り締まらないのですか?」
「彼らの頭は風魔など乱波の一味らしく神出鬼没でな。追えば国境を越えて逃げるから、他国までは役人は踏み込むことが出来ない……それをいいことに好き勝手に生き、裕福な暮らしをしているそうだ」
「とんでもないですね?」
「許せるか?」
「許せません」
「ならば、退治するか?」
「退治ですか?」
「そうだ。良民から奪った金品を取り返して一部は我らの生活費の足しにし、余っ分は飢餓に苦しむ民のために還元させるのだ」
「そう簡単にいきますか?」
「命が惜しいか才次郎、十八歳か? ……もう、充分に生きたではないのか?」
「まだ十八歳ですよ。まだず-っと生きたいですよ」
「ほう、それなら尚更、戦っても死ねんな」
「はい、死ぬ気はありません、生き抜きます」
「よし、明日、山に入るぞ」
主膳がこともなげに言い放って飯を食い、川の水を飲んで再び空を仰いだ。
「雲は流れて消え、消えては現れる」
「鈴鹿山中の追剥のようですね?」
「ま、われらの一生も似たようなものじゃがな。ところで……」
「なんですか?」
「わしは京で暮らすが、才次郎は一度、高野山か伊吹山に上がらんか?」
「高野山は弘法大師空海で存じおりますが、伊吹山とは薬草で有名な?」
「薬草の山とは限らん、伊吹山の松尾寺に提宗という坊主がいる。それに会うのじゃ」
「会ってなんとします?」
「知らん。あとは才次郎次第だ。そこで一生を過ごすもよし、里に出るもよし」
「神社から今度はお寺ですか?」
「修行の日々も悪くはないぞ」
「そうですね、行ってみますか?」
「ま、その前に高野山が先かな」
「僧の修行ですか?」
「いや、おまえに僧は似合わん。煩悩とシャバっ気が多過ぎる」
「いけませんか?」
「なんの、それが若さというものじゃ」
「では、先に高野山に行ってみます」
「そうか、ならば高野山、伊吹山、双方に紹介状をしたためよう」
主膳が荷の中から煙管に似せた道中筆と巻紙を取り出し、達筆な字で簡単な書状をしたため、二通、それぞれ別に油紙に包んで左門に手渡した。
「高野山蓮華谷の三昧寺に秀漢という若い僧がいる。わしの弟分だ、悪くはすまい」
「いつ行ったら宜しいでしょう?」
「明日でも三年後でもいい。京と奈良に飽いたか生活に困窮したら行けばいい」
「承知しました。そうさせて頂きます」
「さあ、そろそろ行くか……」
「山賊退治ですね?」
「そこで死ぬようなら、才次郎もたいした人物じゃなかったことになる」
「大丈夫、彼らの戦利品を巻き上げて飢えた人を救います」
「ほう、気合だけは一人前だな」
左門は先に立ち上がり、秋風を吸い込むように手を広げて深呼吸をした。
33、大和路‐3
飛島村から四里ほど歩き木曽川にかかる尾張大橋を渡るとき、先を行く主膳が振り向きもせずに左門に声をかけた。
「京に上るには四日市、亀山、関から鈴鹿峠越えだが麓の坂下宿まで十里あまり、夕暮れるかも知れんが、歩けるか?」
「大丈夫です。このまま夜の鈴鹿峠まで一気に突っ走りますか?」
「無茶を言うな、鈴鹿峠の山道を越えて次の水口宿までは四里、暗い険しい山道だから何十里も歩くように疲れるぞ」
「では、関宿あたりで泊まりにしますか?」
「ま、峠越えは明日になるかな」
「そうなると、朝一番じゃ山賊は出ませんから夕方まで遊んで、夜、出発ですか?」
「旅の初日は疲れるものだ。ゆっくり静養して体力をつけておく」
「ならば、今夜のうちに山仕事を片づけてから、のんびり静養したいです」
「そんなに山賊退治がしたいのか?」
「それが目的です。宿にいても眠れませんよ」
「そうか。このまま鈴鹿峠越えをするか?」
「ぜひ!」
「よかろう。ならば、坂下宿で腹ごしらえをして、提灯ぶら下げて山道に入る」
「はい」
「賊が出るとは限らない。場合によっては、崖下の窪みで野宿だぞ」
「結構です」
「かといって、このまま急ぎ足では疲れも出よう」
「では、坂下宿でひと休みして、真夜中に出掛けますか?」
「それもいかん。夜明けが近づくと山賊は出ないのだ」
「山賊なら、夕暮れも夜明けも関係ないと思いますが?」
「多くの旅人は亀山か関に泊まって朝一番に鈴鹿峠を越えるのだが、急ぎ旅の場合は麓で夕暮れても、やむなく提灯片手に山越えをすることになる」
「急ぎ旅では仕方ないですね?」
「鈴鹿峠の野伏せりどもは、それを狙って襲って来る」
「待ち伏せですか?」
「そんな無駄なことはせんよ。交代で物見を勤める小者が上り坂の山中に潜んでいて、獲物と見たら、野鳥の鳴き声の伝令で仲間に知らせ、いっせいに近道の間道を走って下り坂で待ち伏せて旅人を襲い、抵抗すれば殺して獲物は山分けにするんじゃ」
「相手が強かったら?」
「野伏せり連中は、強そうな相手には絶対に手を出さん」
「分かるんですかね?」
「長年の経験からの嗅覚とでもいうのかな」
「われわれを、どう見るでしょう?」
「出来るだけ弱そうに見せんとな」
「小柄な田島さまと若造の私です。今のままで充分でしょう?」
「それもそうだ」
「ところで、なぜ深夜だけ賊がでるのです? 夜明けだって同じなのに」
「急ぎ旅でも夜道が怖い旅人は、夜明けの暗い内から山越えをするのだ。これが意外に多くて、十一軒ある坂下宿の宿からいっせいに出掛けるから道中が賑やかすぎて山賊の出る幕がない」
「なるほど……じゃ、やっぱり、このまま峠に上りましょう」
木曽川に次いで、長良川と揖斐川を渡ると、東海道四十二番の宿場町桑名に入る。
揖斐川沿いに旅籠が並び、飯女が玄関先で真っ昼間から客引きをしている。
二つの川をまたぐ長い木橋を渡るとき、左門は川風の冷たさに秋を感じた。
いよいよ他国に足を踏み入れた実感が出て来る。
神社を去るときは、何もかも失うような絶望感に打ちひしがれていた左門だったが、今はもう開き直って、怖いものなど何もない。
主膳が改まって告げた。
「盗賊といえども死に物狂いだ。万が一にも破れたら死ぬことになるぞ」
「それは、神社にお世話になった時から覚悟はできています」
「ならばよい。ここ桑名は松平様の城下町で、脇往還の佐屋街道もここから出ている。才次郎は村正という刀の名は聞いたことがあるか?」
「その刀を眺めると、急に人を切りたくなるという妖刀のことですか?」
「徳川将軍家とも因縁の深い村正は代々続くこの桑名の刀匠でな、初代は室町幕府の依頼で刀を打ったこともあるらしい」
「将軍家との因縁というのは?」
「家康様の父君も祖父も、この村正作の刀で家臣に惨殺され、家康様のご嫡男も正作の刀で斬首、家康様が槍でケガされた時の穂先が村正作……」
「刀匠ではなかったのですか?」
「刀鍛冶は頼まれれば、刃物なら何でも造るさ。鎌の刃でもな」
「鎌で殺されるのは嫌ですね?」
「刀だって嫌だ。そんなことでこの桑名は、焼き蛤、伊勢神宮遙拝一の鳥居、七里の渡しと並んで、妖刀村正で知られるようになったのじゃ」
「なんで七里の渡し、というのですか?」
「なんでって、宮宿までの海路が七里だからさ」
松並木から人家が立ち並ぶ街中に入ると、行き交う人々も賑やかで明るく、開放的な伊勢の雰囲気が感じられる。街道に面して立派な青銅作りの大鳥居が珍しい。
「すごい鳥居ですね?」
「これか? これは百五十年ほど前に、亀山藩七代藩主の松平定重さまが桑名宗社のために建てられたものでな。これだけ立派な青銅作りの鳥居は他にはないじゃろうな。ところで腹はどうじゃ?」
「グウグウ鳴っています」
「何だかいつも空腹のようじゃな」
伊勢湾からの風を快く受けながら旅人の行き交う松並木の街道を四日市に入り、朝明川にかかる橋を渡ると道はゆるやかな下り坂になった。
「四十三番宿といわれる四日市は四の日に市が出てたで地名になった。伊勢参りの分岐点でもあるがな、四日市と拠点でな……」
「賑やかな宿場町ですね?」
「ここには本陣が二軒あり宿は百を越す」
「海路もあるからですね?」
右手に古めいた寺があり、門前の橋を掃いていた僧が主膳に気がつき、あわてて竹箒を横に於いて辞儀をした。
「権宮司さま、どちらかえお出かけですか?」
「峠越えを考えてな」
「明日ですか?」
「いや、今日だ」
「今日? そりゃ無茶ですよ」
「この若い連れが無理にというものでな」
「それはお急ぎですね。提灯をお持ちでないようですが……?」
「麓で求めるつもりじゃ」
「では、長命寺の家紋入りでよろしければ進呈します。門内でお待ちください」
僧が二人を待たせて門内に急いで去った。
参詣橋を渡って境内を覗くと奥に立派な本堂が見えた。
「この寺はな、昔は蒔田という武将が城として使っていたのじゃ」
「どうりで立派だと思いました。でも、この橋はまだ新しいですね?」
「つい八年ほど前に築かれたものだからな」
僧がすぐ、折り畳んだ提灯と火打ち用具と油紙で包んだ小荷物を持った。
「提灯と、団子ですが味噌でくるんでますで二日は持ちます」
「かたじけない」
当然ながら荷物は左門が持つことになる。二人は礼を言ってそこを去った。
主膳も空腹を感じたのか左門に言った。
「四日市名物のなが餅でも食っていくか? 二百五十年前からある店だぞ」
二人は、笹井屋という店に入って餅と茶で休息した後、出発した。
慈音寺越しに亀山城の天守閣を右手の山に見て急ぎ、二人は、夕暮れ時に伊勢参りの客で賑わう関宿に入った。常夜灯があり、本陣、茶店、旅籠が並ぶ宿内では客引きの女の声が姦しい。主膳が、玉屋という旅籠の前で足を止めた。
「どうだ。ここで足を休めて腹ごしらえをし、一気に山に入るか?」
「坂下宿は素通りですね?」
「麓に見張りがいても、ここからの急ぎ旅なら見破れんからな」
こうして、主膳と左門は余分に銭を払うからと、宿に上がって夕飯だけではなく、わらじなども用意させて身支度を整え、提灯に火を灯して宿を出た。
坂下宿の小竹屋脇本陣、梅屋本陣を通り、飯盛女の呼び込みを横目に谷川に掛かる橋を渡っていよいよ鈴鹿峠への山道を入った。
暗い山道に入るとさすがに人影は途絶え、木々が風に揺れる音が不気味に聞こえる。
折しも雲間から顔を出した十三夜の月が、うっそうと街道を覆う樹林の梢越しに二人の足元をまだらに照らした。かなりの急坂を上ったあたりで主膳が足を止めた。
「提灯は邪魔だ。畳んで担いでおけ」
左門が膝を折って提灯の火を消し、畳んで荷の中に包んでいると、主膳が呟いた。
「後に三人、前には……おや、これはすごい数の出迎えだな」
そして、主膳も膝を折り、わらじの紐を結び直す振りをして左門に囁いた。
「その先左に松の大木がある。見えるか?」
「見えます」
「その松の向こう側から左に走り込むとすぐ絶壁に造られた猟師道がある」
「はい」
「では、わしに続け。ここでは相手が多すぎるし!……」
「火縄銃の硫黄が匂ってます」
「よく分かったな。じゃ、ついて来い!」
主膳は、月が雲間に隠れた瞬間を狙ってそのままの低い態勢で風をまいて走り、左門もそれに続いた。
闇夜に銃声が響き、うろたえる夜盗の声があちことで聞こえたときは、すでに主膳と左門は曲がりくねった狭い崖道を急ぎ、彼らの視界からは完全に消えていた。
34、大和路‐4
咲は、法蔵寺八角堂の隠し部屋で叔父の忠吉こと大原忠四郎を介抱していて、成瀬隼人正典の使者から、左門が権宮司に従って京の九条家に向かったことを知らされた。
忠吉が傷の痛みに耐えながら、咲に言った。
「すぐ才次郎さまを追うのだ」
「でも、この傷では……」
「わしに構うな。権宮司を狙って伊賀忍が動くぞ」
「狙いは才次郎さまじゃなくて?」
「柳生の恨みは私怨だが、権宮司は国家の存亡に関わる陰謀に巻き込まれる」
「田島さまは、それをご存じの上で京へ?」
「いや、多分、なにも知らずに招かれてるはずだ。今、幕府を疎んじる天朝さま取り巻きの公卿衆の画策で、天朝さまの御名を拝した檄文が各地の大名に蒔かれている」
「どのような?」
「ロシヤやエゲレスなどの外敵を排除して、一歩たりとも国土を踏ませてはならぬ、というものだ」
「でも、すでに長崎の出島などは交易港として認められているのでは?」
「それも排斥すべし……とな。その公卿の急先鋒が、権宮司を招いた京の九条輔嗣(すけつぐ)だ。その参謀として招かれた田島主膳を上京させることは絶対に許せない。そんな勢力もあるのだ」
「例えば?」
「鹿児島の島津と、外国との交易を進めるべしとする長州などだな」
「ますます分かりません」
「なにが?」
「島津と伊賀忍の関係がです」
「流れ込んだらどうなる?」
「忍びは雇われて動く集団、仕方ないですね」
「少々のことなら秘密裏に進んだのだが、尾張藩に召し抱えられていた伊賀の下級武士にまで声がかかって、櫛の歯がこぼれ落ちるように病気静養の届けが次々に出た。これを成瀬さまが気づき、大道寺の殿を通じてわしに探索の命があったのだ」
「なぜ、わたしに言ってくれなかったの?」
「これは、咲を危険にさらすな、という大道寺の殿からの命で仕方がない」
「でも、今回は田島さまの問題で、才次郎さまは関係ないでしょ?」
「いや、彼らは同行者にも容赦はせぬ」
「どうなります?」
「京には絶対に行かせまいとするはずだ」
「待ち伏せですか?」
「手練(てだれ)の武士を何人か野武士の群れに潜ませて、かなり手強い武力集団で行く手を阻むだろうな」
「街道で危ないところは?」
「やはり、峠越えの山道だ」
「昼間でも襲いますか?」
「並みの盗賊なら夜旅の獲物を狙うが、権宮司の田島さまと才次郎さまが相手なら、こいつらは昼夜に関係ないさ」
「分かりました。すぐ行きます」
咲はそのまま、三味線を抱えた鳥追い女に姿を変えて法蔵寺を出て左門を追った。
旅人が目を疑うような速さで風のように走った咲が、主膳と左門の姿を見たのは四日市に入ってからだった。二人は長命寺の門内にいて僧から提灯などを手渡されていたが、それを横目で見て先を急ぎ、夕暮れ前の鈴鹿峠の坂道を一気に登った。
京への街道のどこかで二人を襲うなら、忠吉の言葉通り鈴鹿越え……どこかに何らかの手がかりがあるはず、と咲は確信していた。
提灯の不要なこの時刻だと、まだ急ぎの旅人が行き交っていて賊の出る気配はない。
それでも、咲の鋭敏に研ぎ澄まされた五感は、峠道の樹林内に潜む野伏せり達のひそやかな酒食に興じながら会話やなどを読み取り、その数が尋常でないのを知った。
咲は歩みを止めずにそこを通り越してから、対面で交差する旅人が絶えたところで樹林に飛び込み、身を低くして林の中を這うように進み、離れた位置の灌木に身を沈めて遠く人声のした樹林の茂みを凝視すると、森の中の草むらに潜んでいる野武士たちの武装集団があちこちに屯している。その数は約五十、半端ではない。
風がおだやかなのに梢が揺れているブナの枝葉を見上げると、銃を担いだ猟師らしき男がのんびりと握り飯などを食らっている。
ただ、伊賀忍びの姿はどこに隠れたのか、咲の視界にはいなかった。
(これだけの人数に襲われたら、防ぎようも逃げようもない)
これが、咲の出した結論だった。
咲は草木の揺れを抑えながらそこから離れ、峠を越えて一気に滋賀側に下りた。
咲が、鈴鹿峠西麓の土山宿の旅籠・松坂屋に着いたときは、まだ夕闇が宿場を包む前だった。玄関先で打ち水をしている佐助という十六歳の丁稚(でっちが)が咲に気づいた。
「お咲さん、お帰り……」
甲賀の里では、帰郷した者をこう言って迎えるのが慣わしだった。
「佐助さん、孝次郎さんはいますか?」 咲がのれんを分けて店内に入ると、その声を聞きつけた宿の主人の孝次郎が奥からすぐ現れた。
「なんだ咲、尾張から帰ったのか? それとも急用か?」
「急ぎの用です」
「用向きは?」
「内々に……」
「分かった。ひとまず中に入れ」
咲は着衣の埃を払って白足袋を脱ぎ、佐助が運んだ木桶の水で足を洗って奥の部屋に入った。
甲賀忍びの頭の一人である松坂屋の孝次郎は、咲の話で事情を呑み込み、すぐに助っ人を集めて峠に急ぐと約束してくれた。
咲は鱒茶漬けを馳走になってから、夜の更けるのを待って、孝次郎の助っ人招集より一足先に、咲は鳥追い女の姿のまま、佐助は忍者姿に衣装を変えて峠に向かって急いだ。
咲と佐助の行く手には、密生する原生林の枝葉に包まれた深夜の鈴鹿峠が雲間越しに見える間道は、両側が背丈ほどもある柴木や雑草にすっぽりと覆われ、月が出ても樹林の中までは見通せない。松明の明かりが夜の峠道を照らし、武装した武士たちが仰々しく道を塞いでいる。
咲と佐助が峠に辿りついたときは、既に戦いは始まっていた。
「逃げ道は塞いだ。もう逃げ道はないぞ。崖の上にまわって頭上から弓と鉄砲だ!」
野武士の首領らしい男が指示する重い声が、夜の静寂を破って咲の耳に入った。
これで、彼らの動きから主膳と左門が逃げ込んだのが松の大木の横から渓谷沿いに続く原生林沿いの曲がりくねった細い崖に造られた細い猟師道であることが分かった。
佐助が咲に囁いた。
「あの道は、いきなり下りになって途中から下りと上りの二股になるだが、そこを下ると二十間ほどで以前の崖崩れ道がなくなってるだ。かと、いって上の道は開けた場所に出るから待ち伏せされたらひとたまりもねえでしょうな」
「なにかいい手は?」
「二人だって言ってたね?」
「そう、一人は小柄で軽い年長の神主さんだけど」
「野ぶどうの蔓でひっぱり上げる手は? おらの下帯でもいいだけど」
「そんなの駄目! 才次郎さんが鼻を摘んで落ちちゃうでしょ」
「おらは、そんな男知らねえだよ」
「あたしの好きな人って言ったら?」
「だったら、お咲さんの帯で引っ張りあげなよ。おれは坊主を引き上げるから」
「坊さんじゃない、神主さんだよ」
「似たようなものじゃねえか」
「帯は、どのぐらいの長さがあれば間に合う?」
「引きやすい場所は、手を伸ばせば四尺(約120センチ)ってとこかな」
「だったら、やってみるわ」
「えらい。さすがにお咲さん!」
「ところで佐助さん、忍び道具の紐はしごは用意してないのかい?」
「商売道具だもの持ってるさ。ふんどしも帯も冗談だよ」
「悪いガキだね。お仕置きだよ」
「喜んで……」
「うるさい。早くその場所に急いで!」
そこで二人は、道なき森の中を藪漕ぎして崖道を上から覗けるという場所に近づいてみると先客がいた。森の外れの崖の上から下を眺めて銃を構えた男と、弓に矢をつがえた男の背が見えた。咲は無言で手を上げ、佐助に弓の男を任せると合図して自分は銃を持つ男の背後に忍び寄って行く。
?
左門は苦戦をしていた。
月に照らされた険しい渓谷の底に岩に砕ける白い泡を筋にして、その一条の谷底の流れが、崖道をやっと歩く左門を奈落の底に引き込むように誘って足元をぐらつかせる。
「才次郎、下を見るな。足元だけをしっかり見つめて歩くんだ!」
主膳はまるで平地を歩くかのように足早に崖道を急いで先を行く。
しかし、左門は崖道の修行など皆無だから断崖絶壁に刻まれた道など歩けない。
背後からは崖道を帯になって続く追手にたちまち追いつかれ、その先鋒が曲がり角から顔を出して槍を突き出した穂先を、辛うじて避けるのがせいいっぱい、足元がぐらついて身体が思うように動かない。その時、種子島の銃声が夜の静寂を破って響き、弓が放たれた蔓音が聞こえた。槍の穂先を避けながら、身軽だからかなり前方まで移動している主膳を見た。
主膳は、崖上から弓と鉄砲で狙われたらしく、上を睨んで崖の窪みにへばりついて動かず、「卑怯だぞ」と、およそ戦場らしからぬ愚痴を言いながら敵の様子を見ている。
左門は、何度も突かれているうちに避け損ねて袖が破れた。この瞬間、腸が煮えくり返るような怒りを感じた途端、逆に冷静さを取り戻し、足元の怖さを忘れた。
すると、相手も曲がり角の不安定な位置から闇雲に槍を繰り出しているのが見え、立場は同じだと分かったとたん、敵の槍の穂先が緩慢で恐れるに足らないことも分かった。
槍の穂先が、左門の胸を狙って突き出すのを待って身体を崖側に寄せて大きく左手を払って穂先下の柄巻きを握って大きく引くと、槍を突いた男が体型を崩してよろめき槍を放した。左門は奪った槍を素早く持ち替えて崖道を戻り、追手を突きまくって見える範囲の野武士を突きまくって崖道に倒したり谷底に落としたりして一通り追手を整理した。
左門は、ゆっりと足元を確かめながら主膳に近づいて行く。
かなり前方から勝ち誇った図太い声が聞こえた。
「逃げ道は抑えたぞ、もう逃げられん。谷底にでも落ちてしまえ!」
背後からは、仲間が倒されたのも知らずに、新たな追手が次々に崖道を追って来る。
「逃げ口は抑えたぞ。二人とも谷底へ落としてしまえ!」
新たに左門を追う男の語尾が消えぬ間に、悲鳴を残して二人の男が谷底に落ちてゆくのを、その男の視線が闇の中でとらえた。
「二人とも落ちたぞ!」
この男の声に呼応して「おう!」と勝ち誇った声が森に響いたが、彼らを追い落としたはずの追手の仲間からは勝鬨どころか何の反応もない。だが、そんなことを気にする者もいない。彼らは、田島主膳を京に入れない、という目的を達したのだ。連れの若造などはどうでもいい。ついでに殺されただけで運が悪かっただけだ。
谷底に落ちる二人を見た男が引き返すのを見て、崖道に入った追手は街道に戻り、前方で退路を抑えた男たちも持ち場を離れた。
?
何がなんだか分からぬ間に、頭上から人間が二人降ったから主膳が驚いた。
その主膳の目の前に、一尺ごとに大きな瘤の付いた縄が音もなく下りてくる……見上げると、その縄の先に月明かりに照らされて見目麗しき女の顔がある。
鈴鹿峠には人をたぶらかす狐が棲息するだけに油断はできない。
物の怪を見たような目で呆然と立ち尽くす主膳は、女狐に並んで縄を下ろしている黒い影も見た。女狐にはもう一尾仲間がいたのか……。
近づいてきた左門の間の抜けた驚き声が主膳の耳に入った。
「咲、そんなところで何をしてるんだ! ここは危ないぞ」
女がかすかに笑みをたたえて手を形のよい唇に当てて「静かに」と言い、手真似で早く登るようにと左門に指示した。
「なんだ、助けに来てくれたのか?」
左門が呟いて嬉しそうに主膳に目配せし、縄ばしごに取りついた。
「いかん、ただの干し草かも知れんぞ」
左門の姿は、女狐とその仲間に引き上げられてたちまち崖上に消えた。
「田島さま、早く!」
今度は左門が小声で喚いている。
(とうとう才次郎まで狐の仲間に堕落したのか?)
それでも主膳は縄ばしごにしがみついた。
狭い崖道で夜を過ごすより女狐に騙されるほうがいい。瘤の部分を両足の草鞋の底でしっかりと押さえたときに、主膳は本物の縄であることを確認し、女の顔を何度か神社の境内で見かけたことも思い出していた。
35、大和路‐5
(こいつは熱田の森に棲む女狐だな)
こう考えると、今までの出来事すべての辻褄が合う。
熱田の森には古くから狐も狸も棲息していて、参詣者の供える御供物や野鼠や兎などを餌に眷属の命脈を保ってきた。世間ではよく狐や狸に化かされたというが、彼らは人間がいじめなければ決して悪さをするものではない。
と考えると、この女狐は主膳との付き合いは長いことになる。
ましてや、神社を拝する参詣者が供えた供物で一族が繁栄していたとなると、とりもなおさず神社を取り仕切る権宮司のお蔭……ではないのか?
主膳は崖上に引き上げられながら考えた。自分が権宮司の時代に、森の狐にどのような善根功徳を施したのだろうか? だが、考えおよぶことはあまりない……それでも、こうして自分たちを助けに来たのは事実なのだ。
(だが、待てよ)と、主膳は考えた。
あのとき、崖の下から才次郎が女狐に「咲……」と呼びかけ、崖上の女狐が早く上がるように手招きしたのは明らかに才次郎であって自分ではない。
ならば、森の女狐は、この春より熱田神社に寄宿した才次郎に一目惚れしたのか?
そこまで考えたところで崖の上に引き上げられ,主膳の目の前に女狐がいた。
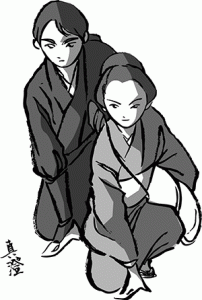
「田島さま。お怪我はありませぬか?」
「わしの名まで知っておるのか?」
「ここは危ないぜ。おらについて来いや!」
忍び姿の小僧が身をかがめて樹林を走ると、全員が後に続く。
それと入れ違いで人声が近づいてくる。
「でかしたぞ」
「谷底に撃ち落としたな!」
振り向くと、かなりの数の松明の炎が崖に向かって走って行く。
「猟師のタケとヤス、いるなら返事ぐらいしろ!」
その声を背に走りながら、咲が主膳の質問に答えた。
「田島さまとは何度か、お目にかかっております」
「そりゃあ、熱田神社の森に何年もいれば見かけることもあるだろうさ」
「いいえ、森ではありません」
「では、どこで?」
「才次郎さまの葬儀のとき。それに、大道寺屋敷でも」
「大道寺? もしかして、お女中の……?」
「咲です。勝手ですがお手伝いにきました。こちらは佐助です」
「なにを手伝うんだね?」
「もしかして、この峠で襲われるんじゃないかと思いまして」
左門が柴木を手で払いながら首を傾げて口をはさんだ。
「咲、山賊を襲うのは田島さまの策で、こっちから襲うつもりだったのだ」
「それが、逆に武装集団のお出迎えだ。山賊もさま変わりしたもんだな」
「あれは山賊ではありません」
「じゃあ、なんだ?」
「田島さまの上洛を妨げる勢力がいるのです」
「なんでだ? わしは頼まれて行くだけだぞ」
「くわしくは知りませんが、田島さまが邪魔なのです」
「わしは、それほど大物じゃないぞ。そんなこと誰に聞いた?」
「それは言えません」
「大道寺の殿か?」
「それも言えません」
「咲と言ったな? 着物姿でその走り、甲賀か?」
「それも言えません」
「熱田で才次郎らが襲われたとき、森の奥を走った女忍と走り方が同じだぞ」
「そうですか?」
「静かに! 待ち伏せされただ」
先を行く佐助が全員を止め、前方をうかがっている。
「逃げきれんか?」
「救けか来るまで、ここで待つだよ」
「切り開けばいいじゃないか?」
まだ幼さな顔の佐助の指示に左門は不服気なのだ。
「相手には飛び道具があるだ。誰か一人やられたら、おらが叱られちゃう」
「まあ、助っ人がくるなら待てばいいさ」
主膳が左門をなだめた。
ほどなくして、孝次郎が率いる甲賀衆が到着したらしく、あちこちで金属音が闇を衝いて響き、声を殺した悲鳴も聞こえてきた。
「さあ、行くぜ」
佐助が立ち上がると、咲が毅然とした口調で左門と主膳に言った。
「ここは私たちに任せて、お二人は佐助に従って土山宿まで突っ走ってください」
「土山宿だな?」
「そこの松阪屋です。わたしの身内で佐助の家ですから安全です。佐助、早く!」
咲はきびすを返して、再び戦いの輪に戻った。
「安心して任せとけって」
原生林を縦横に走る獣道を腰をかがめて走りながら佐助が言った。
「今日の合言葉は、マツ、ウメだからな。間違えんなよ」
原生林から街道に出る寸前の山中で敵が襲って来た。明らかに武士の集団だった。白刃がきらめき、敵味方入り乱れての白兵戦が樹林内に続いた。
佐助が走りながら「マツ!」と叫んで、切りかかる男を切った。その後を走る左門も刀を振るって襲いくる敵を倒し、武具がわりに棒を持つ主膳を守った。
左門と主膳を襲おうとする敵があると、佐助が卍手裏剣を投げて相手を仕留めた。
左門は、ひたすら主膳を守るべく走りながらも周囲に気配りを忘れなかった。そこに現れた助っ人が敵を足止めして参戦した。
「佐助、ここは任せろ!」
「頼んだぜ」
三人はまた走り出した。
天空を低く這った暗雲から激しい雨が山風に乗って落ちて来た。
鈴鹿峠は昔から雨が多いことで知られている。
その鈴鹿峠はまた、東の箱根と並んで険しい峠越えと凶悪な盗賊が出没することでも知られていた。峠道には鏡岩と呼ばれる表面が平らな岩があり、雨に濡れると、まるで水鏡のようにっ遠く坂下宿側から坂を登ってくる旅人の姿を映し出す。
鈴鹿峠は伊勢路の要所だけに、晴れた日の昼間は行き交う旅人も多く、六軒ある茶屋にはいつも名物の白玉と茶を所望する旅人が休息しているだけに、さすがの山賊どもも目撃者の密告を恐れて、滅多に旅人を襲うことはない。
ただ、夜陰に入ると、その岩面が乾いていても旅人のかざす提灯の灯の数が映る。それを見た見張りの山賊が仲間に知らせて襲撃の準備に取りかかるらしい。
さらに、旅人の数が激減する雨の日なども同様に、山賊が出没することがある。
それを知っている田島主膳が、その山賊を襲って今までの戦利品を巻き上げようとしたのが大きな誤算になっていた。
田島主膳と左門を襲ったのは山賊ではなかった。明らかに武士の集団だった。
田島主膳は知らぬ間に、政争に巻き込まれていたのだ。ただ、主膳はその背景をなにも知らない。
横なぐりに吹きつける風が烈しい雨を舞い上げ身体が下から濡れて行く。
それでも、待ち伏せしていた武装集団は土山宿からの助っ人が足止めしたので追って来ない。三人はどうやら危機を乗り越えたらしい。
三人が、ようやく虎口を脱したかに見えたの柄の間、峠道の行く手に新たな敵の集団が見え隠れしている。目をこらしても激しい雨でよくは見えないが、どうやら今度は軍装もないところを見ると浪人の群れらしい。鈴鹿の山賊は浪人崩れが多いと聞く。
「才次郎、今度は本物の鈴鹿の山賊かも知れんぞ」
「心得ました……」
木の枝を手にして身構える主膳の前に出た左門は、左手で刀の鞘を掴み右手を柄において、狙撃を避けるために体型を低くして、山賊の群れを目掛けて走りだした。
「行くでねえ!」
佐助が必死で止めようとしたが、走り出した左門はもう止まらない。仕方なく佐助も走り主膳も続いた。
三人に気づいた浪人の群れは、散るでもなく動くでもなく三人が切り込むのを待っていたが、左門が刀を抜くのを待って隊形を変えた。半分が素早く背後に回り込んで三人の退路を絶ち、いっせいに襲いかかって来たのだ。
雨が激しくなり、左門の視野が極端に狭くなっていた。刀を振るって迫る敵には的確に対応できるが、鋭く繰り出してくる槍には苦しんだ。穂先がほとんど体に触れる寸前で辛うじて身をかわすが着衣は切り裂かれていた。ましてや、矢はまったく見えず、樹上から狙われているのは感じていたが、多数に囲まれての攻防だけに動きが激しく、敵の狙いが定まらないのが不幸中の幸いだった。佐助も主膳もそれぞれ別の輪の中で戦っていた。
何人の敵を倒したか致命傷には至らないのか、峠道のあちこちで呻きが聞こえる。それでも彼らは、後から後からと絶え間なく襲撃の手を休めない。
冷たい秋雨が疲労を早めるのか、左門は徐々に体力を消耗するのを感じた。もはや刀を構え余力もない。まだ二十人近い浪人が左門を囲んでいる。もはや、左門の逃れる道は閉ざされたらしい。左門は、自分が腕が立つだけに限界を知るのも早かった。
突然、走り込んだ佐助が左門を庇うように前に出て、刀を逆手に持って構えた。
松明の灯が佐助を照らした。
「おや……」
後方で戦いの推移を見守っていた群れの頭領らしい男が声を出して近づいて来る。
「佐助……松阪屋の佐助じゃないか? ここで何してる? 危ないぞ!」
「うるさい! おらあ、山賊に知り合いはいねえだ」
「それもそうだな。ほら、おれだよ」
佐助が山賊の頭領の顔を見て、仰天している。
同じ土山宿で軒を並べている同業の旅人宿の主人なのだ。
「鵜飼屋のおやじさん、ここで何してるだね?」
「何してる? 冗談じゃねえ。孝次郎さんに頼まれて落ち武者を待ってるんだ」
「落ち武者は、もっと後でいっぱい来るよ」
「そうか?」
「知らねえから、何人か倒しちゃっただ」
「いいさ。どうせ金でやとったあぶれ浪人だ。身内はいねえよ」
「なんで?」
「この仕事を知ってるのは孝次郎さんだけで、女房も知らねえのさ」
「分かった。じゃあ、たんと稼ぎな。あとからいっぱい落ちてくるよ」
「稼ぐ? なんの話だ?」
「落ち武者の着衣や刀を身ぐるみ剥ぐんだろ?」
「そりゃあ、刀ぐらいは頂くが、着てるものは剥がないよ」
「じゃあ、山賊らしくないじゃないか?」
主膳がたまりかねて、佐助に聞いた。
「こいつが、山賊の頭領か?」
「いや、おらにも分かんねえだ。いつもは旅籠のご主人だけど……」
「分かった。わしが改めて聞いてやる」
主膳が脅すような口調で聞いた。
「おい、鵜飼屋とやら」
「なんだね、坊さん?」
「わしは坊主ではない、れっきとした神主だ」
神主と聞いて男の態度が変わった。周囲を取り巻く殺気だった浪人に手を振って散るように言い、静かになってから主膳に向かった。
「なにを聞きたいんです?」
「おまえが山賊の頭か?」
「人聞き悪いこといわないでください。私は、いま佐助が言った通り、鵜飼屋の勘兵衛という者です」
「山賊じゃないのか?」
「鈴鹿の山賊は、根こそぎ孝次郎さんが雇って、峠の茶屋のほうに連れてってしまいました。ここの連中は、土山宿の旅籠中に声をかけて雇ってきた浪人ですよ」
「誰が雇った?」
「孝次郎さんが金主元です。姪に頼まれて、姪の惚れた男とどうでもいい男と、二人を襲う連中を切ってくれ、という頼みで出張って来ただけです」
「なんだ、面白くもない。誰だ、そのどうでもいい男っていうのは?」
「知りません。ただ、京に上る人だそうで、その上京を阻止する大人数の武装集団が峠に集まっているそうです」
「そいつらは、どこの誰だ?」
「土山宿にも寄ったので知ってますが、西の各藩から集められた武士と雇われ浪人の混成部隊のようでした」
「それと、山賊が戦うのか?」
「おかしいですか?」
「武士とだぞ?」
「いまどきの武士など、実践で鍛えた鈴鹿の野武士に敵うわけがないですよ」
「ほう? 脅すとどうなる?」
「命だけはお助けを、と、自分から下帯一丁になって震えてます」
「じゃあ、そこの若者を脅してみたらどうだ?」
「冗談でしょ? そんな若造……」
その声が終わらないうちに、左門の抜きはなった河内の守助国の白刃が、鵜飼屋勘兵衛の首を襲った。一瞬早く、勘兵衛が五尺ほど横に飛んで首に手を当てて詫びた。
「申し訳有りません。無礼を謝ります。いや、凄まじい剣風でした」
驚いたのは主膳と左門だった。必殺の無礼討ちが見事に外されている。
佐助が呟いた。
「鵜飼屋のオジさんに勝てるのは、忠治郎さんだけだからな」
勘兵衛が苦い顔をした。
「咲にも負けたことがある……わたしはどうも大原一族が苦手でな」
佐助が言った。
「その咲さんの好きな人が、この若いお侍さんらしいよ」
「そうか、それなら納得だな」
「じゃあ、おいらは先に帰るね」
「わしのことは口外するなよ」
「おらだって、松阪屋の跡取り息子なのに、丁稚の佐助で通してるじゃねえか」
「知恵足らずの佐助でな」
「鵜飼屋のオジさん、おらにケンカ売るのか?」
「冗談だよ。ケンカなんか売るものか」
「じゃあ、夜中に玄関に小便掛けるのやめとくよ」
「おいおい、まさか今までに何回か?」
「四、五回かな……冗談、冗談だよ。これでアイコだからね」
「まったく、食えねえガキだよ」
「何とでも言いな。今度はほんとに帰るよ」
「ああ、足止めして悪かったな」
「いいよ、間違いは誰でもあるからさ」
三人は暗い山道を灯火なしで下った。
雨は止み峠道を覆った樹林の梢のはるか上を雲が流れ、時折、薄い雲を通して月あかりが見え隠れしたが、夜目が利く三人にはそれで充分の明るい夜道になっていた。
