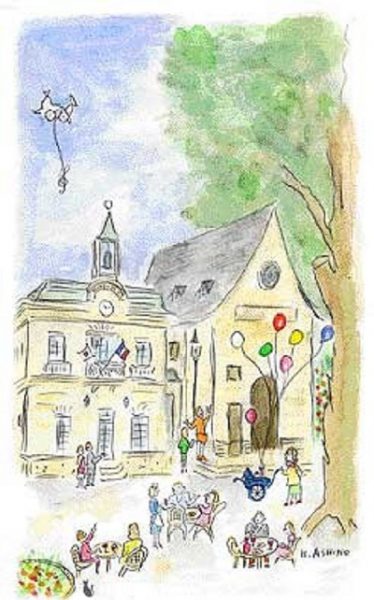
しあわせ
幸福を売る男
芦野 宏
上野をめざす
上田市公会堂で独唱会を聴いてから、胸の中でなにかが激しく変化していくような気がした。
もう私の決心はついた。
中山先生に私が声楽科を志望しでいることを桑原さんから話してもらうと、先生は意外と簡単に教えてくださることを約束してくれた。しかし、一年くらいの受験勉強では無理だから、できるだけ早く上京するようにとのご忠告もいただいた。
上田にいても、足が地につかない毎日だった。ここにいたら受験勉強ができないからである。
十一月二十三日、秋の大運動会が行われ、私は学生代表で実行委員にさせられた。一年下級生の上野君は音楽大好き人間で、彼のお姉さんは「からたち合唱団」のメンバーであり、ピアノも弾ける人だった。それで彼にお願いして、お姉さんにピアノを受け持ってもらい、私が作詞作曲した「秋空晴れて」という曲を開会式典のあとで歌うことにした。
′だれにも言わず密かに決心していたこと、それはこの歌を思いきり大声で歌い、これを最後に学校と別れることだった。
運動会は盛大だった。好天に恵まれ、学生たち有志によってこの歌が歌われた。
「常田(ときた)の丘に 秋空晴れて いま若者よ とび立て自由の大空へ」
大して良い歌ではなかったが、これでお別れだと思ったから声の限りに歌った。
翌日、ひっそりと私は上田を去った。退学届は封筒のまま教務課に出してきた。



