11、襲撃‐1
庄内川に近い烏森の樹林に囲まれた藤三郎の木こり小屋で、密談が行われていた。
風の強い夜だが、小屋の周囲のブナ林が風避けになって、杉屋根に乗せた抑え石の下の重なった杉皮屋根がバタついている音だけがけたたましい。
お互いに押し殺したように声は低いが、充分に会話は成り立っている。
八重が囲炉裏の自在鉤に掛けた狸汁の鍋に菜を入れ、振り向きもせずに声を掛けた。
「長次さん、その、お女中風の女と供の男って何者なの?」
片膝を抱え込んでいる長次という長身の男が応じた。
「後を追えなかったから誰とも言えねえが、あれはただ者ではなかっただ。女は見たこともねえが、男は大道寺屋敷の馬丁の忠吉にそっくりだった。なあ、シゲ?」
「オレも一瞬そう思ったが別人さ。ヤツなら、もっとだらしねえだろ?」
「そうだな。いい女だったが、男共々寸分の隙もなかっただ」
「オレも長次も木の幹に隠れてて、情けねえことに何だか身動きもできなかっただよ」
「やつらの背中に目があるわけじゃねえのに、まったく妙だったな?」
藤三郎が声を出さずに笑った。
「茂三も長次も、蛇に睨まれた蛙じゃあるまいし、なんてザマだ」
「藤三郎兄いと八重姐さんの前で面目ねえが、あの二人はオレらの潜んでるのを見抜いてたのは間違いねえ。なのに、こっちを振り向きもしなかっただ」
八重が煮え立った汁を碗に移しながら、難しい顔をした。
「で、その二人連れは小伜と何を話してたの?」
「それが、顔を伏せたまま歩いていて口をきいた様子もなかっただな」
「だとすると、その大道寺の伜とは関係なったのかも知れないねえ」
「ただの参拝客ってこと?」
「お二人さんは、臆病風が吹いたってわけね?」
八重の一言に長次がムキになって応じ、小柄な茂三が愚痴った。
「姐さん、臆病はねえでしょう? オレも柳生の里じゃ、ちったあ知られた顔だぜ」
「オレだって、姐さんに臆病と言われるのは心外だな」
「だったら、小伜の一人ぐらい、なんとかしなさいよ」
狸汁をすすってから、長次がわめいた。
「あの若造一人ぐらいは、手裏剣一本でカタは付きますぜ」
長次が腕を叩いてイキがり、藤三郎がそれを制した。
「でかい声出すな! 長次も茂三も早まるな。若は表沙汰にしたくないんだからな」
「分かってる。それにしても、藤三郎兄いが次の日に現場に残した草履を拾いに行って、そこから探り出したのが大道寺才次郎だ。よく分かったもんだな」
「あの朝、馬場から外れて馬を走らせた藩内の若者から、割り出したんだ」
少し間を置いて長次がきっぱりと言った。
「相手が才次郎と分かった以上は、誰が止めようとオレは許さねえぞ」
「だからと言って先っ走りぱダメだ」
「柳生の当主は無敵だ。ヤツが若を倒すのに何か汚い手を使ったのは間違いねえ」
藤三郎が頷き、ポツリと言った。
「若の目から小砂利が出た。あれは目つぶしを食らってやられたのだ」
「ますます許せねえ」
長次が懐中から十字手裏剣を取り出して藤三郎に頭を下げた。
「これで心の臓を一発で仕留める。ぜひ、やらせてくれ」
「だめだ。若の許しがねえのに動くとあとが面倒だぞ」
「誰にも迷惑はかけねえ。ここは、オレ一人が勝手に動いたことに」
「屋敷の許しなしでか?」
「すまねえ。皆、知らなかったことにしてくれ」
「そうはいかん。失敗したらコトだぞ」
「邪魔さえ入らなければ、万が一にも失敗はないさ」
「自信があるのか?」
「竹ぼおうきを振り回すのを見たが、隙だらけだった。なあ、茂三!」
「ああ、へっぴり腰だったな」
「今夜でも、一っ走りしてケリをつけて来る」
八重が嘆いた。
「失敗したら、面倒なことになるねえ?」
「失敗はしねえ。寄宿者の宿舎も分かってるし、勝手知った神宮内だ」
「何でそこまでムキになるんだ?」
「あの小伜には何の恨みもねえが、柳生屋敷からの仕事でなにがしかの手当てを貰ってる以上は、主家が恥をかかされたのを見逃すわけにはいかねえだ。これは勇み足でも筋違いでもねえ。誰の指示がなくたってヤルのが、われわれ影の仕事じゃあねえのか?」
藤三郎が頷いた。
「二人には悪かったが、実は、おめえらに様子を見させてから、オレ一人で出掛けて機があればやるつもりだったんだ」
「兄いも人が悪いや。だったら一っ走り仲間内をまわって何人か集めて今晩でも一気に襲ってケリをつけるってえのは?」
「それもいいが、今夜はダメだ」
「なぜ?」
「まだ、どこに寝てるかも確かめてないんだぞ」
「いや、それは神楽殿裏の寄宿舎に間違いねえ」
「それと、あそこには棒術使いや手だれの剣士もいるらしいからな」
「それも大したことはねえ。でも、シゲと今夜もう一度行って確かめてくるか?」
「今夜はオレも一緒に行く。だが、まだ手出しは無用だぞ」
「分かった。じゃあ、明夜ということで。集合場所は?」
「子の刻に神宮の森、本宮のあたりで。合図はフクロウで知らせる」
「一声で応答、二声で集結、三声で決行・・・いつも通り、これで?」
「それでいい。じゃあ、頼んだぞ」
八重が口に指を当てて「シッ」と言い、耳を澄ませた。
風の音に混じって、裏口から草を踏んで動物の走り去る音がした。
「また、むじなか?」
藤三郎が言い八重が頷いたが、長次と茂三には何も聞こえなかった。
「じゃあ八重、ちょっと行ってくるぞ」
「わたしは?」
「おまえの出番は明日だ。楽しみに待ってろ」
立ち上がった三人は、音もなく小屋を出て風のように森を抜けて走った。
12、襲撃‐2
三人は、小屋を出る寸前に着衣を裏返して猿っ袴を穿き黒布で顔を隠していて、黒足袋に草鞋履きだったから月のない夜の闇に染まって、周囲からは一陣のつむじ風が吹き去ったとしか思えない。藤三郎が声を投げた。
「明日の出番だけでも伝えておくか?」
後を追って走る長次が「それがいい!」と応じた。
田を超え畑地を横切って走っていた藤三郎がふと立ち止まって、腕を大きく振って空気をあおり、夜ガラスになりきって羽ばたきながら大きく「短、長、短、短、長、短、短」と抑揚をつけて繰り返し鳴いた。それを真似て長次と茂三も同じように声を合わせて鳴いた。これも、柳生の忍び独特ののろし代わりの通信方法だった。
やがて、近くからも遠くのあちこちからも、それに呼応するように夜ガラスの鳴き声が湧いた。その声だけを聞いた人がいたとしたら、まるで、どこかで死人が出たときのように不気味に感じたに違いない。夜ガラスが鳴くのはそんな夜だったからだ。
ともあれ、これで明晩、忍びの仲間は熱田の杜に集まってくる。
三人の黒い陰は再びつむじ風になって闇を飛び熱田神宮の杜にたどり着くと、西北の下知我麻神社横から迷う風もなく一気に森に入り木々の葉擦れの中に溶けた。
三人の織りなすつむじ風は、広大な森の北に位置する本宮裏の権宮司の居室から土用殿と神楽殿、勅使館から又兵衛館、宝物殿へと吹いてはたと止んだ。
藤三郎が耳を澄ませ、伸ばした右手の先に詰め所があった。闇の中で二人が頷き、たちまち三つの影が板壁に張りついた。彼らが求めている若者の声が、その粗末な建物からかすかに洩れたのを鋭敏な藤三郎の狐耳が捕らえたのだ。
ただちに藤三郎が、明かりが洩れる隙間だらけの板壁に取りつくと、長次と茂三もそれを真似た。藤三郎が目を細めて屋内を覗くと、ゆらぐ灯火の皿からか動物性の脂のにおいが鼻をつき、三人の男がくだけた姿勢で茶碗酒を酌み交わしているのが見えた。すぐ脇に祝い熨斗の貼られた酒樽があるのを見ると、社家から寄贈されたものでもあろうか。
「まあ飲め! 田畑うじも自分だけ飲んでないで、この若者にも注いでやれ」
「弥吉うじは酒癖が悪くていかん、おまえは、もう飲まんでもいい」
「なんの、今宵は左門どのの仲間入りの祝いじゃけん」
酒癖の悪いこの男が長次から聞いた棒使いなら、田畑という武士が剣の使い手か?
町人髷で下男風の弥吉がわめいた。
「1万石大名の柳生など、将軍家指南役の名にしがみついてるだけの小判鮫だ。なんの恐れることなどあるもんか!」
「そんなこと大きな声で言うな。尾張柳生の本家や藩に聞こえたら大変だぞ」
「オレは柳生など怖くもねえ。田畑さんは柳生の大太刀を知ってるのか?」
「4尺7寸(約1・4m)の大太刀か? そんなの実戦で使えるものか?」
「そんな見せ物を、藩主が皆伝だと城へ差し出し、柳生本家の跡継ぎが皆伝になると柳生家が取り戻す……こんなバカな虚礼を繰り返して藩師範の地位を守ってるんだ」
「弥吉うじ、それは言い過ぎだぞ」
「なにが言い過ぎなもんか。昔の柳生は強かったそうだが、今の宗家はどうだか?」
左門が遠慮がちに意を唱えた。
「弥吉さん、それは違います」
「ほう、どう違うんだ?」
「確かに道場では三回に一回は勝たしてもらったが、あれは、わざとだった」
「いや、それが実力だったかも知れんぞ」
「ところが、実際の果たし合いになったら、全く歯が立たないことに気づきました」
「しかし、勝ったではないか?」
「それは……奥の手を使ったからで力の差は歴然、天と地でした」
「どんな手を使おうと勝ちは勝ち、裏柳生に勝っただけでもすごいことだぞ」
下級武士と一目で分かる田畑平三郎が、ためらいがちに口をはさんだ。
「拙者は一度、堂々と兵介のオヤジ殿と相対してみたかった」
「又右衛門厳之さまですか? わたしが教えを受けた師ですが……理由は?」
「柳生の新陰流の源流は元はといえば、伊勢の出の愛州移香斎師から上泉伊勢守信綱師を通じて、伊勢において柳生石舟斎宗厳にと伝えられしもの……」
「それは、存じおります」
「その上泉伊勢守師の供として苦楽を共にして陰流を究めた伊勢守師の甥が、田畑家の遠祖の疋田文五郎と申す武芸者だった……いわば柳生石舟斎の兄弟子、それが、今日埋もれたのは柳生が将軍家の指南役に登用されて陰流がお止め流にされ、陰流を看板にする疋田家は逆境にさらされ人に言えぬ苦労をしたものじゃ」
「いまさら、古い話を持ち出されても」
「祖先の文五郎師は伯父の伊勢守師と研鑽し、甲冑に身を固めて戦場にある時の腰の落とし方と膝の曲げ方に工夫をこらし、三尺を超える大太刀で何人もの敵に勝つ業を編み出した。それが、いつの間にか柳生の「沈(しず)なる身」となって広まった……それだけではないぞ。甲冑を身につけん時は、腰も膝も伸ばしたまま使うのを「つったつる身」などと、もっともらしく極意にしているが、あんなのは疋田だけではない、どの流派でも当たり前のことじゃないか。左門うじはそう思わんか?」
「分かりません。わたしは柳生新陰の本流を学びましたが、ただ……」
「なんだね?」
「別れに際して父親に、大道寺家に伝わる実戦の業を伝え、最後に花を持たせてくれましたが、実際にはまったく相手にならなかったのが悔しいです」
「それよ。世の中には道場剣と実戦剣があるのじゃ」
「柳生は道場剣ですか?」
すぐ返事をせずに、田畑平三郎が燭台の上の皿から立ちのぼる灯火を眺め、屋根を打つ楓の枝葉に耳を傾けてから静かに碗を置いた。
「いや、前言は取り消す。柳生は道場だけじゃないぞ。やはり恐ろしい敵だ」
平三郎は素早く腰から小刀を抜くと、振り向きざまに壁に投げた。
小刀壁に突き立ちくぐもった悲鳴に続いて、小刀を伝わって血が室内に落ちた。
「姑息な手を使いやがって……きさまら、いつでも相手にしてやるぞ!」
素早く立ち上がったが弥吉が戸口に走るのを、平三郎も立って止めた。
「やつらは風だ。もう消えたさ」
平三郎は何事もなかったように小刀を懐紙で拭いて鞘に収め、座りなおすと破れ畳においた碗を手にとり口に運んだ。
それらの光景を、左門はただ呆然と眺めるだけで声も出なかった。
「さあ飲め、飲んで忘れろ!」
弥吉に注がれた酒を一気に飲み干した左門の手の震えが、ひざ頭にも伝わっている。
これは、夜の寒さなのか武者震いなのか自分でも分からない。
ただ、隙間風で揺れていた灯火が揺らぎを止めたのに気づいた平三郎が、一瞬、外の風の強さを屋根を打つ枝葉で測ってから外の敵に刀を投げた凄さ、これだけは忘れない。
この世には恐ろしい兵法者がいることを、左門は酔った頭に刻み込んだ。
しかし、それでもなお、忍びの三人が熱田の杜から逃げたのを見届けてから、静かに杜を抜け出して闇に消えた一つの人影に気づいたものは誰もいない。
13、襲撃‐3
咲は木陰の闇に中腰で佇み、柳生の忍者が逃げ去るのを微動もせずに見送った。
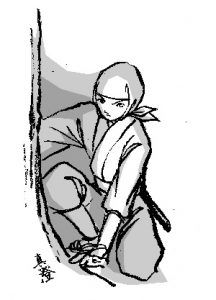
咲は、柳生の忍者らが左門の姿を求めて森の中の建造物を駆けめぐっていた時に、彼らよりいち早く左門のいる小屋を突き止め、内部にいる左門らを覗いていた。服装こそ寺社の作務衣に着替えてはいたが、面擦れの後や目のくばりから一目で兵法者と分かる二人の男に囲まれて左門が茶碗で酒を飲んでいたのを見た瞬間、思わず安堵したものだった。左門を囲む二人の男がただ者ではないのが一目で分かったからだ。
それにしても、燭台の揺れる灯火に照らされて、慣れない茶碗酒を口にする左門の顔が酔いが回ったのか赤く染まって愛らしい。(いけない……)、思いがけない胸のときめきを感じて動揺した咲だが、柳生の忍び達が小屋から洩れる明かりを見つけて、小砂利を避けて森沿いの草を粉で走ってくる足音を感じ取り、素早くその場を離れて樹林の闇に溶け入った。
三人の忍びが、警備小屋の板壁にとり付いた時はどうなるかと不安で心が騒いだ。
しかし、内部から投げられた何らかの武器で忍びの一人が目を潰され、悲鳴こそ上げなかったが重いうめき声が上がったとき、咲の不安は消えた。
傷ついた男は痛みに堪えながら両手を使って刺さった刃先から顔を放すと、二人の仲間に支えられて瞬く間に詰所小屋の裏の森深く姿を消して逃げ去った。さすがに逃げ足は早い。これで、彼らが無理して戦うほど無謀ではないことが分かった。しかも、敵にとっても破れて失うことばかりではない。左門と共にいる仲間が並の武士ではないことが分かっただけでも偵察としての役割は充分に果たしたことになる。
咲はしばらく待ったが、詰所から誰も出て来ないのを確認してその場を離れ、闇の中を走った。もう、柳生の忍びを追うつもりはない。
大道寺屋敷に近づいた咲が土塀に沿って走った。塀に飛び上がって邸内に入ることは容易だが、自分の居宅に潜入するのは気分もよくないし家人の警戒心から思わぬ間違いが起こらないとも限らない。さまざまな理由によって長年の慣習が屋敷内に培われ、咲だけでなく家人全員が正式なとき以外は脇門か裏木戸からと決まっていた。
咲が走る速度をゆるめ、夜鳥の鳴き声を真似て「ピュ-」と指笛を吹くと、中からもそれに呼応して夜鳥が鳴き、裏木戸が開いた。咲が吸い込まれるように邸内に入って木戸を閉じたときは、木戸を開けたはずの人影はすでに消え、「遅かったな」との忠吉の声が残り、「心配かけてごめんなさい。急ぎの報告があります」と咲が応じた。
「緊急情報があるのだな? では、着替えたら殿の座敷で……」
忠吉の声が遠のいた。
女中部屋に戻った咲は、甲賀忍者独特の鼠色の忍び装束を素早く脱いで衣装を着替えて侍女姿に変身し、離れから続く曲がりくねった廊下を急ぎ、屋敷内の母屋にある大道寺玄蕃直方の居間に入った。
先に座して玄蕃と何やら話していた忠吉の横に咲が座って、玄蕃に一礼すると、いつも額に皺を寄せて暮らしている難しい玄蕃の顔がほころんで笑みが浮かぶ。咲には、人の心を癒すさわやかな春風のような和みの素養が備わっているらしく、誰もが心をおだやかにさせられるらしい。これも咲の人徳のなせる技だった。玄蕃がすぐ聞いた。
「どうじゃ。左門は元気だったか?」
「はい。一日目でもう、あちらの皆さんに溶け込んでいました」
「ほう、皆さんとは?」
「昼間、わたし一人で参りました折りは、権宮司の田島主膳さまと親しくお話されていましたし、忠吉さんと替え着をお持ちした折りは田畑平三郎というご家中の侍とすぐに打ち解けてお話されていたご様子です」
「では、今のところは何も問題はないな?」
忠吉が口をはさんだ。
「いえ、それが、左門さまを襲おうとする輩がいまして……」
忠吉に目でうながされ、咲が続けた。
「左門さんに近づいたときに、森の中に忍びの気配を感じたので、腹話で用件は伝えましたが、森に潜んでいた二人組が気になりましたので尾けてみたところ、案の定、柳生に使われている伊賀忍・藤三郎の木こり小屋に入りました。そこで、左門さんを襲う計画が進んでいたのです」
「その伊賀者が襲ったのか?」
「いえ、襲うのは明晩ですがその前段階で左門さんの寝所を確かめねばなりません。そこで彼らは偵察に出たのです」
「なるほど? その伊賀忍の藤三郎もか?」
「藤三郎が手下二人を連れて神宮の森をくまなく探したあげく、侍詰め所にいて二人の神社に寄寓する食客と飲んでいた左門さんを見つけて外壁に張りつき中の様子をうかがったのです」
「咲のことは?」
「先回りしていたわたしには、全く気づかない様子でした」
「隠れたのか?」
「木の陰で闇ですし、彼らは小屋の中に気を取られていましたから」
「ならば大したことない。勝てるな?」
「いえ、この藤三郎は、百地家から出た服部半蔵正成とも血縁のある伊賀忍の名門・千賀地一族の出で人望もあり腕も確かですからこれに勝つのは容易ではありません」
「おまえら、二人では無理だというのか?」
「伊賀忍は数を頼みに攻めて来ますので、相手の人数にもよります。ただ……」
「なんじゃ?」
「左門さまとご酒を楽しんで一緒に酒関宴を開いていた一人が前に述べた田畑平三郎さまという武士で、なかなかの手だれです」
「ほう?」
「板塀の隙間から覗いていた一人を目掛けて小柄か短刀を投げて目を潰しましたから、これは敵も相当手こずるのは間違いありません」
「頼もしいな。田畑といえば家中にもいたな?」
「そこまでは存じませんが……」
「左門の他に二人と言ったが、もう一人は誰じゃ?」
「棒術使いの方かと思います」
「ほう、棒術か? ところで……」
大道寺玄蕃直方が改まって二人を交互に見た。
「左門は、出生の秘密を柳生にそそのかされたらしいがどこまで知ってるのじゃ?」
咲と忠吉が顔を見合わせてから、忠吉が言った。
「柳生も真相は何も知らないはずです」
「しかし、大原の名が柳生から出たそうな」
「大原が甲賀群南山六家の名家であるまでは、柳生は知らぬはずです」
「確かに……そこまでは知らんじゃろうな」
「左門さまには終生、大道寺家ご出身として生きて頂きます。いかがですか?」
「あい分かった。屋敷内外にそれを徹底させよう」
そこで話は終わった。
14、襲撃‐4
深く頭を下げて辞儀をした咲が立ち上がろうとしたのを玄蕃直方が止めた。
「ちと待て……」
咲が座り直したので忠吉も改めて正座して玄蕃を見た。
「左門に付いてゆくというから咲には暇を与えたが、この様子だと左門は動かぬな。しばらくは屋敷に留まり、左門の動向など探索して知らせてくれぬか?」
忠吉も口添えした。
「殿が仰るのだからそれがいい。いずれ左門さまが動かれるまでだからな」
「忠吉は、いつごろまで主膳殿が左門をかくまうと思うているのじゃ?」
「世間の噂では、田島権宮司さまのお立場はかなり危ういようでございます」
「どう危うい?」
「神宮の内部はどの社殿も荒れ放題で雨漏りや床の痛みもひどうございますし、本宮司さまの装束もつぎはぎだらけとか。田島権宮司さまは豪商からの寄進を好まず、町人や百姓からの食料の差し入れ以外は受け付けませんので貧しいばかり……実権を握られて何も出来ぬ本宮司さまは、次期に入れ替わる権宮司馬場家との交代を早めるよう画策中と聞き及んでおります」
「田島が失脚しては左門もいられまい。それは何時ごろになろうかのう?」
「長くて二年、早ければ半年というところでしょうか」
「そうか……咲はどうする? 昨日は三味線抱えての鳥追姿であったが?」
「まだ、左門さまは世間を知りません。心配が失せるまで後を追うてみます」
「咲は左門をどう思うているのじゃ?」
「どういう意味でございますか?」
玄蕃直方がまっすぐ咲を見た。
「好きか、と問うたのじゃ」
咲が恥ずかしそうに下うつむいて小さい声だがきっぱりと答えた。
「好きでございます」
玄蕃が頷き、忠吉が微笑んだ。
咲は、森の中のあばら家で寂しく眠るにくであろう左門を思った。
春とはいえまだ夜の寒さは厳しい……左門を思うと咲の胸は痛んだ。
左門は眠れなかった。
存分に酒を飲んだ棒術の棚原弥吉は、本宮裏の権宮司宅に警護役として寄宿していたのでそちらに戻り、田畑平三郎は飲み潰れて寝所に用いている詰め所の破れ畳の上で横向きで大イビキをかいている。
左門は飲み慣れない酒を浴びるほど飲んだのだが、酔いが醒めてくると春の夜寒が身に滲みてくる。敵がいつ襲ってくるかと思うと睡る気にもなれない。左門は押し入れから引き出したせんべい布団を平三郎にかぶせようとすると、今までイビキをかいていた平三郎が姿勢を変えて目を開き横たわったまま身構えた。さすがに反応が早い。
「ああ、布団をかけてくれるのか?」
左門を見て安心したのか、また平三郎は目を閉じていびきをかきはじめた。
神宮内には社務所に働く巫女をはじめ宿舎に住み込む男女も多く、動員すれば10人や20人の助っ人は集まるが柳生の忍びに対抗するほどの者はいない……平三郎からはそう聞いていた。ならば、助っ人は平三郎と弥吉の二人だけ、それで闘えるのか?
左門も押し入れから出した破れ布団にくるまって仮眠したが、酔いの醒めた左門は悶々として眠れぬ夜を過ごしすことになった。
早くも刺客は左門の身辺に忍び寄っている。これから先は、どこに逃げようとも命は狙われる。その覚悟で……と、自分に言い聞かせてはみたが、まだ十八歳の左門には無理な話だった。初恋の甘い夢も消えた。恋しい早苗はどうしているか? 一人の女をめぐって意地になり命のやりとりをして敵をつくった自分は正しかったのだろうか?
思えばまた心が乱れる。
家族に捨てられ愛を失い、強力な敵に追い詰められて死んでゆくだけなのか? 考えれば考えるほど不安がつのり、絶望感だけが心に闇を広げてゆく。これから先、どうすべきか……左門にはもはや考えても追われつづけて死ぬだけなのか? 生きる道は? どこに逃げおうせれば柳生の追手から逃れられるのか? 起きてしまったことは仕方ない。気にするな……と、いくら自分に言い聞かせても無理な話だった。左門の頭の中は混乱の細い糸が絡んで蜘蛛の巣状態になっていて、結論の出ないまま堂々巡りを繰り返して際限がない。それでも、明け方には睡魔に襲われていた。
「おい、起きろ! 朝飯前に庫裏の掃除だぞ」
咲に優しく起こされていた昨日までと違って、先に起きた田畑平三郎に布団を剥がれての覚めが出奔最初の朝だった。
神楽殿のお符場の軒先に置かれた風呂敷包みから、左門が日常に着慣れた衣類を出そうとすると平三郎が押し止めて、棚から洗い晒しながらきちんと折り畳んだ茶色の作務衣を手渡した。
「今日から大原ウジはこの神社の社男だ。参拝客には頭を下げ親切に案内し道を清める。
痛んだ家屋を修復し、酔って参拝客に絡み神聖な神社にあだなす酔漢などは、断固としてつまみ出す」
「私達が酔うのはいいのですか?」
「へ理屈を言うな。われらは参拝客に絡んでおらんじゃないか」
手水場で顔を洗って、ひとしきり平三郎についてまわって掃除をした後、朝食を共にするために本宮裏に隣接する権宮司宅に向かった。参道から脇道に入って広葉樹の生い茂る森を抜けると、あちこちで桜がほころび初めていた。
「もうすぐ、この参道も桜並木に変わるぞ」
平三郎が目を細めて桜のつぼみを眺めた。
その横顔からは、腰に差した小刀を抜いて壁に投じた時の鋭い眼光の険しい殺気の気配はない。昨夜、刺客を傷つけた刀を鞘に収めてからの平三郎も、その事件の前となんら変わらぬ表情で共に酒を酌み交わしていたが、なぜ、そんなおだやかな気持ちでいられるのかが左門には不思議でならなかった。
熱田神宮の本宮は森全体の西北に位置し、権宮司の仮宅はその裏手にあった。本宅は尾張城の外堀近くにあるらしく多くは語らないが、この熱田神宮の実験を握る権宮司という役職も田島家の専有ではなく、遠祖が大宮司家から出た兄弟の馬場家との交替制であり、時代によって権力の座も変わっていた。
田島主膳はその最中に権宮司という大役を背負っていたが故に、ここで大道寺家と柳生家を巻き込む事件など起こしては身の破滅……強いては一族の浮沈に係わるだけに、左門をここにおくことの危険は百も承知のはずだった。昨夜の出来事も弥吉から聞いてすでに知っているに違いない。
しかし、田島主膳はそのような思いは少しも見せずに笑顔で左門を迎えた。
「ここで眠るように言ったのに、酔いつぶれて平三郎と詰め所に寝たのか?」
「はい」
弥吉は、平三郎と左門に軽く会釈して何事もない表情で麦飯を盛り汁を出した。
「田畑さんの小刀を投げた時の、あの見事な早業には驚きましたぞ」
弥吉が平三郎に碗を手渡しながら、思い出したように感嘆の言葉を投げた。
左門は主膳を見た。神宮内は刃物は厳禁と聞いたが、平三郎は小刀を用いて平然として恥じる風もなく、主膳もまたそれを責める気配もない。
そうなると、相手が刀を用いても藩に告訴することも叶わぬから白刃相打つ肉弾戦になるやも知れない。その左門の思いを読んだのか主膳が三人に告げた。
「これから刀を抜くことはならぬ。昨夜の件はおおやけに出来ぬが、柳生側が白刃を見せればがこれからのことは藩にも公儀にも報告せねばならぬ。したがって、そちたちは間違っても刀を使うではない。よろしいか?」
「承知つかまつりました」
平三郎が頭を下げ、弥吉は表情も変えず、左門だけが即答できなかった。
「才次郎……いや、左門は不承知か?」
「いえ、承知しましたが、やはり棒がよろしいでしょうか?」
「棒に自信がなければ、樫の木の木刀もあるぞ」
「それをお借りします。やはり、昨日の棒では心もとなくて……」
「そうか、それもよかろう。弥吉、木刀を用意してやれ」
そこで話題が変わり、食事が始まった。
朝の食事は一汁二菜の簡単なものだったが食欲の出ない左門の喉を通らない。
それに引き換え弥吉と平三郎は健啖で、黙々と飯も汁もお代わりをしている。
ふと、平三郎が笑顔で呟いた。
「今日一日の飯が今生の別れになるやも知れんからな」
主膳が頷いた。
「わしなど、とうからその心境で生きとるわい」
弥吉が左門を見た。
「どうした。敵に襲われるのが怖くてのども通らんか?」
それを聞いた権宮司が、おだやかに言った。
「食べたくなくても汁をかけても流し込みなさい。いま体力を失うと、忍びの集団の粘り強い夜襲には対応できまいからな」
左門は無言で飯に汁をかけ、無理に口に流し込み朝食を終えた。
これで死んだら悔いが残る。なぜかそう思った。
田島主膳がおだやかに言った。
「左門は今日はなにもせんでいい。充分に昼寝して体力をつけなさい」
弥吉と平三郎が頷いたところをみると、やはり心配だったのだ。
15、襲撃‐5
「そろそろ現れる刻限かな?」
作務衣の下に鎖かたびらを着こみ新しい草鞋を履いた武装姿のまま布団にくるまっている平三郎が闇の中で呟いた。服装は三人とも同じだった。
弥吉が応じた。
「敵はこちらが手ごわいと見て、数を揃えて来るぞ」
弥吉も眠ってはいなかったのだ。
左門が布団の中で身震いを抑えるように、寝返りを打ってから言った。
「どのぐらいの人数で?」
「拙者には分からん」
「多分……」
身を起こして布団の上に座った弥吉の表情が、ゆらぐ灯火に照らされて恐ろしいほど険しく精悍に見えた。左門は庄内川の河原で死の恐怖を超えて闘ったあのときを思い出していた。あの時と同じ恐怖と忘我の境地を味わうに違いない。
弥吉が言った。
「十二から十五……平三郎うじのあの鋭い技を知ったからには数を揃えて来るさ」
「思ったより手ごわいかも知れんな」
「どうする、外でやるか?」
「外はいかん。包み込まれて手裏剣の餌になるだけだ。ここで待ち伏せして一人一殺を四回繰り返せば終わりだ。左門さんは木刀で敵の手足を封じてくれればいい。彼らの刀は一尺五寸……木刀は三尺余りだから小手を打って骨を折れば手裏剣は投げられぬ。外へ出たら距離をとられて負けるが、室内なら勝ち目はあるからな」
「火をかけられたらどうする?」
「火をかけられた場合は戸口を蹴倒して囲みを破り、三人一緒に向かいの参詣者休み所に走り込む。あくまでも室内で戦うのだ。間違っても森に入るな。手裏剣で蜂の巣にされた上でなぶり殺しにされるぞ」
平三郎の言葉にうなずいた弥吉が、ふと布団から半身を起こした。
「どうした?」
「田畑さん、なにか聞こえなかったか?」
「拙者にはなにも……」
「しっ……静かに」
弥吉が二人を制して目を閉じてうつむき、じっと耳を澄ませている。
平三郎がけげんな表情で左門を見たが、左門にも風にそよぐ森の木々の枝葉のざわめきの他は何も聞こえない。
弥吉が二度ほど頷いて、「有り難う」と呟き、目を見開いて顔を上げた。
「まだ遠いが敵が十数人、現れたそうだ」
平三郎が不審な面持ちで弥吉に聞いた。
「おぬしは、今、誰と話したのだ。拙者には何も聞こえんぞ」
左門も弥吉を見た。
「天の声だ」
「バカな……味方を欺くのはよせ」
「悪かった、正直に言うよ。誰か知らんがわれわれに味方するという者がおってな。風に乗せてきつつきの文を送ってきたのだ」
「きつつきの文とは何だ?」
「きつつきという鳥を真似て、ブナの幹を小柄の刃先で突ついて伝言する。甲賀忍びの一部で用いられている忍びの術でな」
「おぬしが何故、そのような術を知ってるんだ?」
「これ以上は言えん、命が惜しいからな。ただ、ここでは伝言を伝えるだけだ」
「なんて言ってる?」
「助っ人は二人だ。森から出ず姿も見せず、直接の戦闘にも加わらない」
「高見の見物か? それが敵の陽動策だったらどうする?」
「そうかも知れんが、信じてみる価値はあるぞ。伝言は、敵の全員を引きつけてから一気に外に出て暴れてほしいそうだ」
「そいつらは、ただ、我々がなぶり殺しになるのを見たいだけじゃないのか?」
「だが、それが一番の良策ならやってみる価値はあるぞ」
「ダメだ。外で闘えば三人の力がバラバラになる。三人で力を合わせて室内で闘って一人づつ抹殺してゆく。外に出るのは最悪の時だが、目の前の休憩所に飛び込むのだ」
「よかろう。その前にひと暴れすれば助っ人の文が本物かどうかが判るからな」
確かにどちらにも一理ある。そうと思った左門は、素直に頷いた。
兵三郎が布団の中に押し入れから引き出した余分な夜具を詰め、三人が寝ているように細工し、それぞれの布団の端に紐をつけ、三本の紐の端を左手に持ち、右手に木刀の柄を握って戸口にへばりついて左門に命じた。
「灯火を消せ」
左門が燭台の蝋芯からゆらぐ炎を吹き消すと、室内は闇になった。
「これでも彼らには苦もなく見えるが、しばらくの間でいい。三人が熟睡していると思わせて独りづつ中に引き入れ、自分の布団を刺した瞬間に背後から脳天を叩くのだ」
「細工が知れたら?」
「そこからは筋書きはない。一緒に行動し、危なくなれば一気に外に出る」
そこからは会話は消え、室内の闇に消えた。
弥吉がまた耳をそばだてた。
 「いよいよ来たぞ」
「いよいよ来たぞ」
左門は、板壁に身を寄せて外の気配を感じ取ろうとした。すると、左門にもひたひたと玉石を避けて森の草を踏んで忍び寄る微妙な足音が感知できたのだ。生きるための本能が獣のように五感を研ぎ澄ませてくる。見回すと真の闇に思えたあばら家のあちこちに壁の隙間からの明るみが差し込んでいて、布団には確かに誰かが寝ているように見える。
だが、外からこれを見たとき、微動もしない寝姿などあろうか。すぐ見破られてしまうだろう……こう思ったとき、誰もいないはずの布団が動いた。驚いて飛びすさると、弥吉が「しっ」と低く注意して闇の中で平三郎を見るように顎をしゃくった。
左門が戸口に立つ平三郎を見ると、闇の中で白い歯が見えた。平三郎が左手を上げて笑ったのだ。それで、ようやく布団の端に結んだ紐の役割が左門にも理解できたのだ。
板壁の隙間から覗き見ると、月はないのに闇に慣れた目は夕暮れのように遠くまで見通せた。
やがて、黒い影が闇の中で動きはじめた。
敵は、西門の菅原神社裏から一人づつ腰を沈め、足音を殺して忍び寄って来る。
と見えてきた。
平三郎も弥吉も板壁の隙間から目をこらして、敵の動きと数を頭に入れていた。
ここからはお互いの会話は禁物、手真似だけで意思の疎通を計らなければならない。
敵は、一人また一人と壁に張り付いて屋内の様子を窺っている。
左門が覗いている目と鼻の先に敵がへばりついたために左門は動きが封じられ、粗くなる呼吸も抑えなければならなかった。幸いに風が強くなって屋内側の呼吸までは外からは読めないはずだ。
頃合いをみて平三郎が紐を引き、布団の中でもぞもぞと人が動くように操作する。これが見事に効いた。外から屋内の闇を覗く忍び達の目を見事に欺いたのだ。
忍びの全員が、寝ているのは三人で襲撃に気づいていない……そう信じたらしい。
板壁を挟んで左門に接した忍びが、右手を上げて「行け!」という合図をし、まず自分から動いた。これが忍びの頭領なのか?
戸口にまわったのは三人で、よく見ると、後に続いた一人は覆面の中の片目が布で覆われている。と、なれば、田畑平三郎の刀を受けた男もさすがに忍び、あれだけの重傷にもめげずに一党に加わったのは敵ながら天晴れというべきだろう。やはり、柳生忍びも恥をかいたままでは名がすたるのか。
先発の三人が、寝ている相手を赤子の手を捻るよりたやすく一人一殺で刺殺して昨夜の仇を討つ……忍びの誰もが三人の刺客でこと足りるのを信じて疑わなかった。布団の動きからして確かに熟睡しているのは間違いないからだ。
目標は大道寺左門だけだったが、冥土の土産と昨夜の仇……この三人を消せば何の証拠も残らない。これを見届ければ全員が風のように引き上げるし、三人がし損じた場合は全員で一気に襲いかかってなぶり殺しにするだけだ。忍びの集団から徐々に緊張感が消えつつあった。
藤三郎が巧みに手裏剣として使う小柄の刃先で、戸口の内側から閉じた閂(かんぬき)を音もなくこじ開けながら長次と茂三に目配せし、誰がどの位置の相手を刺すのかを決めてから一気に戸を開くと夜風とともに躍り込み、それぞれが逆手に持って振りかぶった忍び刀の切っ先を布団の上から力いっぱい突き刺した。
その瞬間、ギェ-という蛙が踏みつぶされたような悲鳴が屋内に響き二人が絶命、一人が重傷となったのだが、その攻守が逆転していて、襲ったはずの三人が背後からの急襲であえなく朽木のように倒れたのだ。ただ、藤三郎だけは左門の脳天への一撃を巧みに避けて肩口で受け立ち直って反撃し、接近戦になった。左門は必死に木刀を振るったがそれもたたき落とされ敵の刃先を避けて懐に飛び込み組み打ちになる。
そこに、外からその光景を見た敵がなだれ込んで来て乱闘になった。
