36、忍びの里-1
「いま、帰ったよ!」
「お帰り……」
玄関の引き戸を開けた佐助の目の前に、家族や番頭がいた。
深夜にもかかわらず土山宿の旅籠「松阪屋」では、家族をはじめ全員が起きていて、孝次郎・佐助親子の帰宅を待ちわびていたのだ。
女将らしい女性が、左門と主膳の姿を見て形を改めた。
「いらっしゃいませ、佐助の母、志津でございます」
主膳がおうように頷き、左門が低く頭を下げて挨拶をした。
「世話になります。大原左門と申します」
「大道寺の若様ですね?」
「それは昔のこと、いまは一介の素浪人に過ぎませぬ」
「事情は存じませんが、咲が大変お世話になりました」
「こちらこそ」
「何はともあれ、まず、お上がりください」
志津が改めて主膳に向かい、深々と頭を下げた。
「熱田神社の宮司さまとお見受けします。むさ苦しい宿ではございますが、ごゆるりとお休みください」
「ほう、わしのことも知ってるのかね?」
「熱田神社の祭事には何度かお伺いして、お顔を拝見しています」
「それは嬉しいことだ。田島主膳でござる。もう宮司ではないがな」
孝次郎の妻の志津は、親子とも帰宅は明け方かと思っていたのが、息子の佐助が暗いうちに客人を連れて無事に帰宅したのだから大仰に喜ぶのも無理はない。
松阪屋は、土山宿でも知られた旅籠だけに宿泊する旅客も多いが、この日は泊まり客を他の宿に移して、万が一に備えていた。
桶に水を入れて運んで来た女中が、水をたらいに移し二人の足を濯いで、ていねいに雑巾で足を拭き「ごゆるりと」、と頭を下げた。
志津に案内されて二階の部屋に入ると、真新しい浴衣と手拭いが用意されていた。
「狭い部屋しか空いていなくて、お二人ご一緒で済みません」
「なあに、相部屋でも文句は言えないんだからな」
「お食事の前に、お湯にどうぞ」
志津は、二人のことを何くれとなく気づかった。夫をはじめ出掛けた者が帰還したときにいつでも入れるように大きな檜づくりの浴槽には湯が溢れていて、主膳と左門はのんびりと湯浴みをして、宿の浴衣に着替えると、二階に吹き抜ける夜風が快い。他に客がいないから宿の中も静かで戦いの後の気持ちの昂りもおさまってくる。
志津と女中の二人で、熱燗徳利に魚の干物付きの茶漬けを乗せた膳を運んで来た。
「お構いしませんが……」
「これは、かたじけない」
志津等が去ると、主膳が遠慮なく杯に手酌で酒を満たして旨そうに喉を鳴らして飲み始めた。それを見た左門も、自分の膳についた徳利に手を伸ばすと主膳が笑った。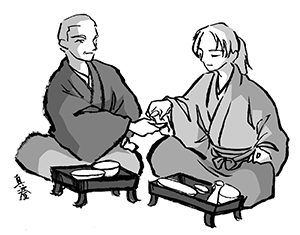
「才次郎も、酒を覚えたか?」
「はい。兵三郎さんと弥吉さんに仕込まれました」
「いいさ。酒は百薬の長……度が過ぎれば気違い水だがな」
左門が、先刻来の疑問を口にした。
「咲が、田島さまの上京を阻む者がいる、と言ってましたが、どういうことですか?」
「なにかの間違いじゃろう」
「でも、なぜ、あそこまで執拗に私たちを狙ったのでしょう?」
「まったく心当たりがないな」
「田島さまは、なぜ、九条家に請われて行くのですか?」
「冠婚葬祭、祭事などの差配かな?」
食事が終わると、女中が膳を下げ夜具を用意して去った。
「明日があるから、寝ておけ」
飼い猫なのか、戸の隙間から部屋に入りかけて左門の顔をチラと見てすぐ去った。
それを見た左門が呟いた。
「もうすぐ丑の刻の後(午前二時)ですね?」
「ほう、才次郎は猫の目読みをどこで学んだ?」
「咲に教わりました」
忍者が住む家では、必ずといっていいほど何匹かの猫を飼っている。真夜中の子の刻(11時-1 時)では猫の黒目は見開いていて、白昼は黒目が線のように細くなる。
大道寺屋敷でも咲が飼い主として許されて猫を飼っていて、左門はそれを用いての猫の目時刻調べを教わっていた。それも、晴れた日と雨の日など周囲の暗さに合わせての変化も読み取ることが出来るようになり、左門は、いつの間にか猫の目さえ見れば、ほぼ間違いなく時刻を知ることが出来るようになっていた。
咲は、夜陰に乗じて左門の部屋に忍んで来るときも、愛猫のヨネを抱えて来ることも多かっただけに、左門が猫の目時刻を知る代償にヨネには咲との情事を見られていたことになる。
左門は疲れ切った身に僅かではあったが酒が染みて睡魔には襲われているのだが、咲のことが気になってなかなか眠れない。咲が、まさか自分のために追ってきて命を助けてくれたとは信じ難いことだった。かといって、あの鈴鹿峠の近い間道の崖の上から左門を見た時の、闇の中の谷明かりに浮かんだ咲の表情は、ゾッとするほどの愛情に満ちていた。崖道から引き上げられたときに触れた手のぬくもりも忘れられない。
(咲には命を助けられた。この借りは返せるものだろうか?)
今はまだ、自分の行く末も明日も見えず、咲のことまで考えても仕方がない。
大道寺家にいたときは何の変哲もない家事見習い修行の女中としか思わなかっが、その後の咲の変貌には驚くしかない。左門は咲が甲賀村のくノ一だったとは知るよしもなかったが、思い返してみると、身のこなしも何となく軽やかだったし、猫の目時刻だけではなくあらゆる雑学についての博識ぶりに、何となく思い当たる節がある。その咲が、帰郷の途次で偶然に左門の危機を見かけたとは思えない。
と、なれば、左門を追って来た可能性も……そのとき、睡魔が左門を襲った。
どのぐらい眠ったのか、かすかな物音で意識が覚めかけると、廊下からふすま越しに佐助の声がかすかに聞こえた。
「お二人さん、起きてますか?」
左門が答えようとすると、先に主膳が応じた。
「帰って来たのは、あるじだけではないようだな?」
「よろしければ下で一緒に茶でも、とオヤジが言ってます」
「すぐ行く」
「寝巻のままで結構ですので」
「そうさせてもらおう。下に何人いるんだ?」
返事はなかった。すでに佐助は音もなく階下に去っている。
左門と主膳が階段を下ると、咲が迎えに来て部屋に案内した。
すでに明け方に近く、帰還したばかりの孝次郎らを囲んでの密談が続いていた。
咲が、左門と主膳を上座に据えてから正座し、二人に一同を紹介した。
「この家のあるじ、松阪屋の孝次郎。わたしの叔父に当たります」
左門は初対面だが、主膳は違った。
「どこかでお会いしてますかな?」
「熱田さまには、わずかですが寄進させて頂いております」
「そうか。祭事の折りにお見えになっておったようですな」
主膳は、記憶があいまいな時はこれで通すのだが不思議にこれで通じるのだ。
咲が続けた。
「志津さん、佐助さん、鵜飼屋の勘兵衛さんは、峠でお会いしたそうですね」
「妙なかたちでな」
勘兵衛が顔をしかめた。
「このお二人と佐助には、えらい目にあわされた」
それには触れずに咲が主膳を見た。
「こちらは、熱田神社の権宮司で……」
それを制して主膳が横柄に続けた。
「田島主膳だが熱田の宮司は退官し、新たな居住地に移動中じゃ。この若者はわしの縁戚で大道寺才次郎……改め、今の名は何じゃったな?」
「大原左門と名乗っております」
「大原左門か? と、いうことじゃ」
主膳、左門を上座に、孝次郎、勘兵衛、志津、咲、佐助の七人が車座になって座り、女中がそれぞれの横に簡単な菜と具、徳利などを乗せた盆を置いて去った。佐助だけには酒がない。不服を唱えたが誰も相手にしないので渋々と渋茶を飲んだ。
「では、話を続けてくれ」
孝次郎の一言を待っていたように、鵜飼屋の勘兵衛が孝次郎に詰問した。
「こちらの田島さまが、そもそもの発端なのか?」
「咲、説明してくれ。勘兵衛さんが不服らしいから」
主膳がけげんな顔をしたが無理もない、主膳は未だに詳しい事情を知らないのだ。
37、忍びの里‐2
「先刻来、府に落ちないことばかり続いているが、わしがどうしたのじゃ?」
困った顔をした咲が、それには答えずに勘兵衛に向かった。
「勘兵衛さん。なにがお気に召さないのですか?」
「いい仕事になる、という孝次郎さんの言葉を信じて、宿場中を駆けずり回って宿泊中の浪人さんを集めて出張っただに獲物はなく、このお二人と佐助に切りまくられてケガ人が続出というありさま。今、村医者の座敷は地獄図だぞ。その浪人たちの苦痛に耐える呻き声を聞いたら、ここにいる全員が少しは気が咎めるはずだ。それに出費も嵩むぞ。何でこうなった? 誰か説明してくれ」
孝次郎が腕組みをしたまま、深刻そうな顔で応じた。
「金は約束通り全部払うよ」
「金もだが、真相を知りたい。どこだか知らんが西の雄藩の選ばれた武士ってえのは真っ赤な嘘か?」
「それは本当だ」
「ならば、なぜ奴らは現れなかった。四十人からの選ばれた武士が一体全体どこに消えたのだ。佐助もじきに落ちて来る、と言ったのに」
それには応えずに、孝次郎がため息をついて声をひそめた。
「太平の世が続いて、甲賀も落ちぶれたもんだ」
「なんだ、逆切れか?」
「違う。勘兵衛さんのことじゃない。他の甲賀衆のことだ」
「そんなことは判ってる。話をはぐらかすな!」
「黙って聞いてくれ。問題は違うところにあるんだ。まず金は先に払う」
志津が苦い顔をする。
「うちに、そんな余分な金、ある訳ないでしょ?」
孝次郎が膨らんでいた懐中から分厚く重そうな袱紗を取り出して開き、黙ったまま無造作に中身の金子を掴んで畳に並べた。
まとまった一両小判の二十五両束が四つ……百両、首が飛ぶどころではない。
志津だけではない。全員が絶句して息を呑んだ。
「こんな大金、どうしたの?」
志津の声が震えを帯びている。
「孝次郎さん。こんな大金、どこから盗んで来た?」
「落ちぶれても甲賀の孝次郎、盗みは……場合によるが、これは違う」
孝次郎が話すか話すまいか逡巡している様子に志津が気づいた。志津は、気まずい雰囲気を解きほぐすように口をはさんだ。
「咲の話だと、峠での相手は江戸の薩摩屋敷などから選ばれた腕すぐりの刺客ばかり、その網をくぐって、あの二人をよく助け出せたねえ」
「あの二人なら、自分たちだけでも切り抜けられたのよ」
「いくら何でも、相手の武士が強かったら無理でしょう?」
「さあ、わたしと佐助は、崖下の道にいたお二人を引き上げただけだから」
「じゃあ、その四十人以上もいたお侍はどうなったの?」
勘兵衛が苦い顔をした。
「わしが孝次郎さんに聞いてるのは、そのことよ。山賊どもと闘えばかなりの乱戦になって双方に相当の死人やケガ人が出る。そこで痛み分けになれば、山賊は仲間の死体を担いで山に逃げ、疲れ切った武士は命からがら土山宿に落ちる……そこを襲って浪人共に切らせ、金品や金目の物は切り取り自由にさせる。そう約束した」
今度は佐助が口を出した。
「そいつらは、オヤジさんが雇った鈴鹿の山賊に散々な目に遭ったらしいよ」
「それじゃあ、落ち武者になって、この宿場に逃げ込むわね?」
「ところが、鵜飼屋さんが宿場中から腕の利きそうな浪人を集めて待ち伏せしたから、オヤジさんの雇った山賊に痛めつけられたから手負いの武士はいるはずだよ」
「でも、そこには一人も現れなかった。」
勘兵衛が鋭い目で孝次郎を睨んだ。
「さあ、この小判のことも含めて真実を話してもらおう。何があったのだ?」
全員が孝次郎の口許を見つめた。いや、佐助だけは退屈そうに欠伸をしている。
「これを話す前に……佐助、一通り家のまわりを見てきてくれ」
「分かった。天井裏まで調べてくるよ」
孝次郎が瞑目し、それぞれが沈黙を守った。
佐助はさほど待たせずに戻って来た。
「異常なし……どこにも人気はないだよ」
頷いた孝次郎が重い口を開いた。
「ここから先は口外無用、いいかね?」
全員が頷いた。こんどは佐助も仲間に入っている。
「志津、六軒ある峠の茶屋で今、一番人気のあるのはどこだ?」
「それは、うちにも来る坂井屋さんに決まってるだろ?」
「坂井屋さんは、昔から人情家で知られている。困った旅人がいると茶菓代を無料にするなど日常茶飯で、名前も聞かずに路銀を貸したり、あれでよく生業が成り立つものだ、と心配するものもいたが、坂井屋の長兵衛さんに言わすと、損して得取れ、で、あれだけ繁盛すれば充分、元はとれるそうだ」
「その茶屋がどうしたんだえ?」
「わしが関の地蔵院の講に月に一回通う往来に立ち寄るのも坂井屋さんだ。それで、いつの間にか長兵衛さんとは肝胆相照らす仲になり、うちにも何度か泊まってるだろ?」
志津が頷き、佐助が口を尖らせた。
「あの長兵衛さんか? うちに泊まったときに床の間の掛け軸の裏の壁を押してたのを見たことがあるけど、何だかうすっ気味が悪い人だったな」
「そうか、そんなこともあったのか?」
孝次郎が納得したように頷き、志津も首を傾げた。
「あの長兵衛さんは、いつもニコニコしていたが目は笑ってなかったね」
苛立った勘兵衛が孝次郎を促した。
「長兵衛さんは昔から知ってるが、わしは好かん。それがどうした?」
「長兵衛さんのことを、仏の長兵衛、地獄耳の長兵衛というのは知ってたか?」
「仏の長兵衛は知らんが、地獄耳の長兵衛と言われてるのは知ってるさ」
「その長兵衛さんが、咲より先に田島さまを襲う計画のあることを知っていて、妙な話を持ちかけてきたのだ」
「どんな?」
「もしも、その時に助っ人が必要なら言って欲しい。必要な人数を揃えて駆けつけてくれる野武士の頭領を知っている、と言うのだ。その時は、妙なことを言うと思っていたが、咲が駆け込んで来てから甲賀衆の家々を走り回って声をかけたがムダだった。そこで長兵衛さんを頼ってみて、それが本当のことだと知ったのだ。長兵衛さんが狼煙を上げたら、たちまち山の中に賊が集まったのだ」
「情けないが、もう、孝次郎さんでも甲賀衆を動員できないことを、長兵衛は見抜いていたのだな?」
「太平の世が続き、忍びの出番は無くなった。いつの間にか、どの家も修行をしなくなって戦闘能力を失っていたのだ。これで、もう甲賀は力を失った……だが、それだけじゃないぞ」
「なんだ?」
「長兵衛さんが口を利いて集めたのは、間違いなく鈴鹿山に巣食う山賊でかなり強力な戦闘集団だった」
「それは聞いた」
「だが、その鈴鹿の山賊が、根来衆の末裔だと知ったら?」
「まさか? 根来衆はとうに滅びたはずだぞ」
左門は、古い時代の根来衆のことはおぼろげに聞いていた。
かつて、比叡山の僧兵といえば、なまじの大名をしのぐ軍事力を誇ったものだが、それ以上に強力な勢力を誇ったのが紀州の根来寺だった。根来寺一山は堂坊・宿坊だけで二千七百余を連ね、数万の僧兵が日夜の修行に武術の鍛練を取り入れて武力を高め、戦乱の世に勢威を振るっていた。それを苦々しく思っていたのが、織田信長の死後、天下統一を果たした豊臣秀吉だった。しかし、根来衆は、各地の有力大名を従えた秀吉にも屈せず、その一大勢力をもって天下人の豊臣秀吉に逆らっていた。
それを怒った秀吉は、天正十三年の春、各大名に令を発して根来寺全山を焼き払い、逆らう僧兵だけでなく命乞いする者をも容赦なく殺戮し、その残虐さは離散して各地に隠れた根来党一族の恨みを買っていた。
その根来衆の残党の一部を密かに召し抱えたのが、秀吉に反目する徳川家康だった。
秀吉の死後、関が原における天下分け目の決戦に徳川方にあって、攪乱戦法で西軍を悩ませた上に、家康の本陣を守って奮迅の活躍をしたのが忍者集団の根来衆だった。
家康は、天下一の地位を奪った後に尾張藩を創設し、四男の忠吉を入府させた。その折、付け家老として成瀬正成を江戸から送って犬山城主に赴任させたが、その時に家康が成瀬家に密かに預けたのが、その根来衆の一部であることが、同時に名護屋入りした大道寺家の記録にも残っている。
「根来衆か……?」
勘兵衛が腕組みをし眉間に皺を寄せた。
38、忍びの里‐3
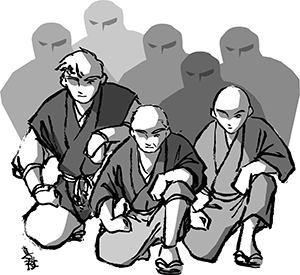
「鈴鹿山の山賊が根来衆の子孫らしいという噂はあったが、まさか本当とはな?」
勘兵衛が呻くと佐助が口をはさんだ。
「おらは、とっくに知ってただよ」
「なんでだ?」
「山に入ってりゃ、山賊のガキとも遊ぶし喧嘩もするからさ」
「そうか。孝次郎さんも知ってたのか?」
「うすうすはな」
「そうか。彼らは今の世までも徒党を組んで何を企んでるんだね?」
田島主膳が口を開いた。
「熱田神社の若い神官にも根来組の末裔が一人いたが、成瀬様のお屋敷にいる根来衆とは日頃から連絡を密にして、お互いに頻繁に出入りしておったな。彼らは血の誓いによって堅く結ばれているそうでな。全国の神社仏閣に入り込んで神事仏事に供奉しながら隠忍自重して天下騒乱の時を待っていると聞いたことがある」
志津が聞いた。
「騒乱の時に何をするのです?」
「根来寺に往時の繁栄を取り戻すために各地で蜂起して暴れるだろうな。彼らの祖先は僧兵として威を振るい、天下を統一し関白となった豊臣秀吉にも逆らった。その結果、一族郎党を無残に焼き殺された天正十三年の恨み……これが百三十近く過ぎた今でもまだ種族の怨念となって、平穏な世の中に向かって仇をなすのじゃ。紀州の山野を駆けめぐり、武芸と仏の教えによって鍛えた彼らの強靱な心身は、この太平の世にあっても並々ならぬものがあるからな」
「それと、旅人を襲うのとはなにか違うような気もしますが?」
志津の疑問には答えずに主膳が続けた。
「国家統一を果たした家康さまは、本能寺の変で三河まで逃げ帰る際に、道中を守って命を助けられた恩義ある伊賀や甲賀と違って、根来衆にはさしたる義理はない。だが、生き残った僧兵の武術や兵法を惜しみ、その窮状と豊臣憎しの心情を買って、一人三十俵二人扶持という薄給ではあったが徳川家の臣として雇いあげた。その一部が尾張藩の付け家老として犬山城の城主となった成瀬正成の家来や御庭番として雇われ、甲賀や伊賀とも共存するようになったのじゃ」
咲が呟いた。
「そう言えば、法蔵寺にも根来衆らしき僧が何人かいました」
「なるほど、それなら、この大金も納得できるような気がする……」
孝次郎が金包みを見て呟き、かなり真剣な口調で言った。
「この金は、わしの仕事を長兵衛さんが買った代金なのだ」
全員が孝次郎を見た。勘兵衛がきつい口調で孝次郎に問いただす。
「あんたが、長兵衛さんに頼んで根来衆を助っ人にしたんだろ?」
「そうだ」
「だったら、彼らを雇った孝次郎さんが日当を払う立場じゃないのか?」
「それが、事情が変わったんだ」
「どう変わった?」
「わしは長兵衛さんから、山賊は浪人崩れと聞いていた。まさか、根来衆とはな」
「しかし、うすうすは知っていたと言うたではないか?」
「うすうすだから確証はなかった」
「そのことはもういい。それで、どう変わったのだ?」
「根来衆の山賊は、めったやたらに強かった」
「荒修行の根来衆の子孫じゃな。待ち伏せの西国武士はみな殺しか?」
「さにあらず、全員、殴り倒されからめ取られて縛られたのだ」
勘兵衛が佐助を睨んだ。
「さっき、武士たちは山賊と乱闘していると言わなかったか?」
「そんなことは言わないよ。山賊にやられてると言っただけだよ」
孝次郎が続けた。
「田島さまの上京を阻んだのは、鹿児島藩の武士だけではなかった」
主膳が腕組みをしたまま妙な顔をした。
「ますます分からん。どこの武士がわしを狙うのだ?」
「京の公家衆が、尊皇攘夷を旗印に幕府に反抗しているのはご承知で?」
「知っているが攘夷など絵に描いた餅じゃ」
「どういうことです?」
「我が国にオランダ船が流れ着き、アダムスが江戸に来て、幕府が貿易を許してからすでに二百余年になる。その間に、スペイン、ポルトガル、ロシア、イギリス、アメリカの船が続々と北から南にと現れて通商を迫っているのは知っているな?」
「噂では……」
「頑丈な船には優れた武器も積んでいるらしい」
「戦えば?」
「負けるさ。なのに鎖国だの攘夷だのとは、愚かなことではないか?」
「しかし、田島様は、その攘夷論者の巣窟でもある九条家に招かれたのでは?」
「わしは神官じゃ、九条家の神事を束ねるのみで政治には興味はござらん」
「各藩の隠密はそうは見ていません。田島様が動けば全国の神社とその信奉者が攘夷に加担すると見ております」
「勘兵衛さんとやら」
「はい」
「そのような戯れ言を、どこでお聞きなさった?」
「この噂は甲賀の者なら誰しも存じおること、無論、孝次郎さんも咲もです」
「孝次郎さん、間違いござらんか?」
「その通りです。ただ、咲の言うには、前途ある大道寺家の若様を田島様の道連れにはだせたくない……何としても鈴鹿峠で引き止めたい、とのことでした」
「わしに付いて才次郎が京に上るのは反対だ、と申すのか?」
「さようでございます」
「ならば言おう。わしは、残り少ないこの命ある限り、目まぐるしく変わる天下の動きをこの目で見てみていたいのじゃ。昨年のイギリス船の長崎来航での船長談話からもれ聞こえた世界のことに興味をもって以来、わしの心は青年のように沸き立っている。誰か、アメリカという国がいつ出来たか知ってるか?」
そんなことを誰も知るはずもない。
「才次郎はどうだ?」
「知りません」
「わしが生まれてからだぞ。なんとまだ四十年も立っていない。つい二十年ほど前にワシントンとかいう男が頭領になった国だ。そんな国が大きな船に乗って遠い異国に貿易を迫ってくる……そんな世の中になっているのだ。昔からあったロ-マという大帝国が二十数年前に滅び、フランスという国では王様が国民の暴動で殺されて国政が変わり、ナポレオンという将軍が皇帝になってロシアまで攻め入ったとも聞く。これで、この日本が変わらぬはずはない。いずれ、日本にも革命のうねりが来る。幕府を報じて万世まで平穏にという佐幕派は滅びる。だからといって、我が国の土を一歩たりとも外人には踏ませまいという攘夷派なども姿を消してゆく……才次郎!」
「はい」
「おまえが生きている内に、この国には関が原以上の戦いがあるやも知れんぞ」
「はい。しかと覚悟しておきます」
孝次郎が聞いた。
「そこから、どうなります?」
「分からん。ただ、日本中が二つに割れるのだけは間違いない。わしは、それを承知の上で九条家に行くのだ。多分、光格天皇さまにもお目見することにもなろう。わたしは尊皇ではあるが攘夷ではない。身を呈しても大きなお心になられて国を開かれるように進言するつもりじゃ」
勘兵衛が心配げに言う。
「そのような田島さまのお考えがお公家衆の耳に入ったら、すぐに石見銀山を茶に混ぜられてあの世行きですよ。触らぬ神に祟りなし……」
「神に触れるのがわしの仕事でな。ともあれ、国は開かれてこそ発展するものじゃ」
「長崎以外でも、異国との交易が出来るようになるのですね?」
「いずれ、尾張藩も尊皇攘夷組と、幕府に与する佐幕派とで血で血を洗う争いになるやも知れぬ。大道寺の殿もお気の毒よのう」
「なぜですか?」
「家康公が西国大名への備えとして九男の義直さまを尾張に入封された折りに、竹越、成瀬の有力な武将を付け家老として送ったのがそもそもの因縁で、今や両家は水と油のように相入れぬ仲、しかも成瀬家と大道寺家は先祖代々、石高には差があれど家老として親交があるのは、才次郎も承知の通りじゃ」
「知っております。かつて北条家の武将で上州松井田の城主だった大道寺家の祖も、秀吉さまの小田原攻めに破れた後、前田利家預けとなりましたが、その武勲を惜しんだ徳川家康が譲り受けて重臣として遇し、成瀬家が付け家老として尾張に移封された際に招かれて尾張藩に入って重臣になった経緯があり、成瀬家とは一蓮托生の縁と思います」
「そうか。大道寺家とは遠縁ながらわしも縁者、間違いがなければいいがのう」
思慮深そうな主膳の顔を、左門は黙って見つめていた。
39、忍びの里‐4
暫くの沈黙の後、左門が我慢できずに口を開いた。
「近いうちに何か起こりますか?」
「尊皇攘夷とか幕府に与する佐幕派というのも確たるものではない」
「と、いいますと?」
「尊皇攘夷の行く先は倒幕、すなわち徳川幕府を倒すことにつながるからな」
「幕府を倒す? とんでもないことですね?」
「一方では、それを防ぐために皇武合体を企む勢力もある」
「皇武? 朝廷と幕府が合体ですか?」
「ま、現状ではあり得ないことじゃがな」
志津が聞いた。
「これからの日本はどうなりますか?」
「幸いに、今の将軍・家斉さまは聡明なお方じゃ。近いうちに日本は大きく変わるが、その時には才次郎、おぬしは捨て石になれ。どうせ勘当された身だ。何らかの形で新しい日本に役立ってみろ」
「はい!」
勘兵衛にとっては、それどころではない。目の前の百両が気になるのだ。
「孝次郎さん。長兵衛はなぜ、この仕事をこんな大金であんたから買ったのだ?」
「捕らえた武士にそれだけの価値があるからだそうだ」
「百両なんて、もったいない」
「しかも長兵衛さんは、山賊の根来衆にも同じ金額の百両を払ったんだぞ」
「山賊に百両? 頭がおかしいんじゃないか?」
「子分どもは、跳ね上がって喜んでたな」
「でも、その山賊は孝次郎さんが雇ったんじゃないのか?」
「わしと根来衆は面識もない。長兵衛さんが頼んだから馳せ参じたのだ」
「長兵衛は、一体全体何者なのだ?」
「茶屋のオヤジだ」
「そんなのは知ってる。われわれだって旅籠のあるじだ」
「長兵衛さんはこう言った……わたしは商売人だから損はせん。今回はいい仕事をさせて貰った。この金を甲賀村の再興に使うように、近いうちに必ず天下が引っ繰り返るほどの騒乱の時代が来る。そのときの為に準備しておいてくれ、と……こう言いやがった」
「聞いた風なことを。でも、ただ者ではないな。で、どこかの藩の武士はどうした?」
「こうも言った……武士の命はわたしが買った……これが、この百両だ」
「それで?」
「武士を木に縛りつけて、江戸の薩摩屋敷や長州屋敷に早飛脚で知らせて、書面にしたためた金額で引き取るかどうか返事を貰う、その場でいい返事がなければ、そのまま世間を騒がせた謀反人で旅人を襲った盗賊でもあることを記して書面を奉行所に届け出て、報償金を貰うことで手を打つという」
「しかし、飛脚に返信を読ませるのか?」
「飛脚? 根来衆も忍びの修行をしているのだぞ」
「そうか。早飛脚も根来衆か?」
「長兵衛さんの凄いのは、その後の言いようだ」
「なんと言った?」
「山賊にこう言った。藩にも幕府にも無視されるようなら無用の者、身ぐるみ剥いで谷底に突き落とすなり、狼の餌にするなり勝手にしていいぞ、となんとも凄まじい言いようだったな」
「その場合は、二百両は捨て金か?」
「わしも気になって、それを聞いたら、長兵衛さんは、わたしは、これを元にいくらでも稼げますのでご心配なく……と、面白そうに笑っていたんだ」
「ますます、うすっ気味わるいヤツだな」
主膳が口をはさんだ。
「元はと言えば、このわしのことから出たことで迷惑をかけた。その山賊どもの棲み家はどの辺りか分かるかね?」
孝次郎が手をついて頭を下げた。
「田島さま。悪い了見はおやめください。鈴鹿の山賊退治は、藩主からのお声掛かりで散々、我々も協力しましたが山が深く、賊が三子山にいるまでは分かっていますが棲み家までは突き止めた者がいません。彼らとわれわれ土地に住む者とは何百年もの長い間、共存共栄で過ごしてきましたし、彼らは山で迷ったり谷に落ちた村の子らを助けてはくれますが、宿場の者を襲ったことはありません。そう無闇に山賊退治などと言わんでください。この宿場が山賊の敵に回ったら、みんなが迷惑します」
「ほう、あんたは山賊の肩をもつのかね?」
「肩は持ちませんが、無用の争いは好まないだけです」
改まった孝次郎が金の包みを一つ、主膳の前に押し出した。
「これは、田島さまと大原さんでお分けください」
「なんでだ?」
「お二人は、鈴鹿の山賊を脅して路銀の足しにしようとしたのではありませんか?」
「ほう、図星だが誰に聞いた?」
咲が言った。
「わたしが言いました。そうとれる節があったからです」
「その通りだ。才次郎の路銀にな。山賊退治は無理だったようだな?」
「無理より無茶です。咲のためにも才次郎さんを危ない目に合わせないでください」
「分かった。これは才次郎が頂いておけ」
「そんな大金……」
「いいさ。素直にもらっておけ」
左門が誰にともなく頭を下げ、二十五両の切り餅を懐中に入れると、ずっしりとした金の重みと、恐ろしいほどの冷えを肌で感じた。

孝次郎がもう一つ、今度は勘兵衛の前に金の包みを出した。
「勘兵衛さんには、これで……」
「これじゃあ多すぎる。浪人の日当と治療費だけで十両もあれば」
「そうはいかんでしょう。多分、ごねる浪人も出るでしょう」
「では、遠慮なく」
孝次郎が包みを一つ出して、志津に頭を下げた。
「おまえには、苦労ばかりかけている。これで家の中、着るものなぞ任せる。咲にはこの中から五両ほど分けてやってくれ」
眠気が出たのか舟を漕いでいた佐助が頭を上げた。
「おらの分はどうした? 存分に働いただに」
咲が笑った。
「わたしが三両頂いて、その中から佐助に一両上げるけど、それでどう?」
「一両なんてバチが当たっちゃうよ。おらは一朱銀ひとつで大金持ちだ」
「分かった。一朱でいいのね? だったら、わたしは二両だけ頂きます」
孝次郎は黙って、残りの切り餅ひとつ二十五両を再び勘兵衛の前に出した。
「勘兵衛さん」
「なんだね?」
「これを元手にして、忍びの甲賀として再興を図ることは出来まいか?」
「この二十五両でか?」
「鵜飼屋さんの遠祖は甲賀の頭領……人質となって育った徳川家康が今川家に背いたき、織田信長と組んで今川の難攻不落と言われた西郡城を攻めた折に、甲賀衆約三百名を引き連れて参戦して城内に深く潜入して火を放ち、敵を大混乱に陥れて落城させた功のある甲賀切っての勇将だった……」
「お互いに、今でこそお互いに旅籠の親父だが、両家の先祖は共々に、本能寺の変で信長公が討たれたとき堺にいて孤立した窮地の家康が宇治川を渡って甲賀の里に逃げ込んだのを救い、それを伊賀党が継いで無事に伊勢の白子浜まで送ったことか、関が原でも重用されて面目を施し、以後、一族の一部は幕府に仕えてはいるが」
「だが、残った一族は仕事もないから、忍びの修行など辛いだけで意味がないと、誰も忍びの修行をしなくなった。したがって、どの家にも装束はおろか忍び刀、忍び熊手や手裏剣、水ぐももない。これでは、いざ鎌倉となったときに何の働きも出来まい」
「その通りだ。田島さまのおっしゃるように、近く天下分け目の大きな争いが起こるのであれば、こうしてはいられまい。根来衆や伊賀者に負けない甲賀の意地も見せてやらねばならんな」
「まず、甲賀二十一家に、忍びの鍛練を促す回状をまわす」
「その下を含めて五十三家にしたら?」
「いや、二十一家のうち数軒はすでにない。上が動かねば下は無理だ」
「大原、鵜飼、滝、上野、望月、隠岐、和田、山中、伴、夏見、針、宮嶋、青木……あとはどこだった?」
「大原は三軒、望月と宮嶋、隠岐が二軒で全部で十八、ま、こんなところかな」
勘兵衛が咲を見た。
「ところで、咲……」
「はい」
「叔父の久兵衛はどうしてる? 大道寺家に仕えていると聞いたが?」
「あのう、久兵衛とは忠四郎さんのことですか?」
「忠吉という名もあるそうだな?」
「叔父は今、傷ついて床に臥せっています」
「ならば、妙薬を遣わすから傷が癒えて動けるようになっら籠に乗せて連れて来い。ここは、久兵衛と咲に甲賀の里の再興を賭けるしかないんだ」
「でも……」
勘兵衛が左門と咲を交互に見て微笑んだ。
「分かっておるわい。わしも野暮は言わん。そちの大切な人には京には行かせん。鵜飼屋の用心棒になって頂く、それでどうじゃ?」
左門がためらわずに言った。
「わたしは残りません。田島さまに付いて京に上ります」
「腕ずくでも行かせん」
「腕ずくでも行きます」
「若造、甲賀の勘兵衛を甘く見るなよ」
勘兵衛が鋭い顔で立ち上がって構えた。その姿には一分の隙もない。
40、忍びの里‐5

立ち上がった勘兵衛を、座ったままの孝次郎がなだめた。
「まあまあ、鵜飼屋さんの気持ちも分からぬではないが、才次郎さんにも考えがあっての上洛だと思うので、ここは一歩引いて、好きなようにさせて上げたらどうかね」
「それもそうだな。ま、せっかくの食事と酒だからあり難く頂くか」
大人げなく息巻いたのを恥じたのか勘兵衛が、きまり悪そうに腰を下ろして、目の前の卓にある徳利と杯に手を出した。その顔は人の良さそうで旅籠のオヤジに戻っている。
食事中の咲が箸をおいて、控えめに言った。
「わたしは、尾張に戻って忠吉さんの様子をみてきます。体が回復するようなら、わたしが大道寺家にお断りを入れた上で、連れ帰って参ります。忠吉さんなら、今後の甲賀村の再興に役立つのは間違いありません」
「咲はその後、どうする?」
孝次郎の疑問に咲が迷いなく答えた。
「好きに生きさせて頂きます」
「甲賀の指導者になってくれぬのか?」
「わたしは、もう誰にも拘束されたくないのです。でも、日々の修養は実践で続け、身をもって世の中のために尽くし、甲賀にも恩返しをしとう存じます」
「そうか」
「わたしが倒した同じ忍びの伊賀の方々に対しても、それが礼儀でもあり供養にもなるかと思いまして」
「それも一理あるな。好きにするがいい」
「ありがとうございます。甲賀の里には必ず恩返しをさせて頂きます」
咲がチラと左門を見た。咲はひたすら左門を見守って生きるつもりだったのだ。
左門は、まだ咲の決意には気づいていない。ただ、好きに行きたい、と言った咲の真摯な表情が、まぶしいほど輝いて見えたのも新鮮な思いがした。
それと、とうに滅びたと思っていた甲賀や伊賀の忍びの組織が、かつては戦国時代各大名の手足となって活躍した頃の勢威は失って弱体化したとはいえ、いまだに滅びることなく組織とし命脈を保っていたことにも左門は驚いていた。しかも、長年にわたって自分の身のまわりの世話をしていた咲が甲賀一のくノの一だったとは……。
さらに、自分が住み慣れた尾張からほど近い鈴鹿の山中に、とうの昔に滅びたはずの僧兵軍団である根来衆の残党が、山賊になってしぶとく生き残っていることにも目を見張る思いがした。
昔、鈴鹿山には鬼丸という山賊がいて悪事を重ねていたという故事は、左門も幼いときに周囲から聞かされていた。だが、まさか、国家統一を果たした豊臣秀吉にさえ歯向かった強力な根来寺の僧兵が野に下ってこの山に籠もり、何代もの世代を継いで新たな天下騒乱に向けて復権のための牙を研いでいる。この一事を知っただけでも左門の血は騒いだ。
今も昔も、この鈴鹿山脈が滋賀と三重にまたがる忍者の里であるのは間違いない。
かつては、夜盗や山賊を業とし、渡りスッパなどと呼ばれた浮浪人が戦国武将の諜報活動に使われていた時代もあった。その機動力を買った各武将が食録を与えて雇ったのが抱えスッパで、これが、奇抜な奇襲戦法を術として発展させた忍者の前身と聞く。
この忍びの術は、戦乱の世の重要地点として鈴鹿山系に絡む里人の切磋琢磨による錬磨によって、孫子の兵法や和漢の教典を学び、術として発展させたものだという。
それが、明智光秀の謀叛による本能寺の変によって天下人の織田信長が殺され、小人数の家臣と泉州堺にいた徳川家康が孤立して明智の追撃を受けながら命からがら三河に逃れた時、甲賀・伊賀の忍びの集団に守られて、無事に脱出できたのだ。家康はその恩義に感じて、江戸城に入ってからも正門を甲賀衆、裏門を伊賀衆に配備し、その上の御庭番として重用したことは巷間によく知られ、左門でさえ忍者といえば鈴鹿山系の山々を思い浮かべるのだ。
それにしても、生き抜くということは大変なことらしい。
左門は、若くして勘当された身である上に、これからの天涯孤独な身の上を思えば、いくら一人で力んでも何一つとして実現出来るとも思えないが、それでも、自分がこのまま埋もれてゆくとも思いたくなかった。
何らかの形で世のため人のために尽くして、この世に生きた証を残したい。これが十八歳まで育ててくれた大道寺家への恩返しになる。若気の至りで家を捨てた悔恨や悲しみよりも、好むと好まざるとに係わらず未知の世界に進むしかない自分の運命を、左門は前向きに享受する心境に至っていた。
部屋住みとはいえ尾張藩三千五百石の家老の家に安住していた左門には、見ること知ることの全てが新鮮で珍しかった。尾張にいた頃の日々は、朝起きてから寝るまでが決まりきった暮らしだったが、今は毎日が波瀾の連続で息を抜く暇もない。それがまた、左門の好奇心を煽る。と、同時に未知の世界に向かうことを思うと身震いするほどの恐怖に襲われることがある。
主膳との旅は京で終わる。そこからは天涯孤独な一人旅となるのは間違いない。
それでもなお、孤独な流浪の旅に生きなければならない宿命を背負ってしまった自分を哀れんでもいられない。明日もまた夜が明ければ、新たな旅の一日が始まる。
その旅は孤独だが、孤独なのは自分だけではない、咲もまた孤独なのだ。しかも、流浪の旅は自分や咲だけではない。神国日本もまたエギリスなど世界の列強にもまれて大海に漂う小舟のように目標を見失っている。
いずれ日本は世界の列強として開国しなければならない時期が来る、と主膳は左門に言った。その主膳があろうことか、鎖国して朝廷復活による国政を願う攘夷派の黒幕でもある九条家に招かれた田島主膳……その意味も知らずにお供として随ってきた自分の無知さにも左門はおのれを恥じた。
左門は目を閉じた。
その主膳の話では、いずれ日本は国を開いてっ世界と交わるという。夢のような話だがあり得ないことではない。その主膳が言った言葉が頭に強く残っている。
「日本は大きく変わる。その時には捨て石になれ」
自分にそれだけの器量があるとは思えないが、左門は、この孤独な身を天下国家に捧げることに未練はない。では、天下国家とは何だ? 国とは朝廷のものでも幕府のものでもない。民の集まりがあってこそ国家ではなかったのか? ならば、国家の捨て石になるということは、世の表舞台から忘れられて貧しく暮らす人のために自分を捨てることでも叶えられる……その覚悟ができるか? 左門は自問自答していた。
「どうした才次郎?」
主膳の声で目を開くと、勘兵衛が言った。
「田島さまも大道寺の若さまも一期一会のご縁でしたが……その立場がいかようになろうとも、いざ、という時は、この甲賀土山宿の鵜飼屋の勘兵衛にお声をかけてくだされ。いかなる時でも、一党を率いて馳せ参じますぞ」
主膳が笑った。
「また浪人を集めるのかね?」
「とんでもない」
「では、長兵衛とやらに頼んで鈴鹿の山賊を動員するのかね?」
「田島さま、お言葉ですが甲賀にも意地があります。もう根来衆の手は借りません。それまでには、甲賀忍びの地侍をみっちりと叩き直して戦う軍団に仕上げておきますので、ご心配なく」
「それは頼もしいな」
「それと、なぜか分かりませぬが、大道寺の若さまであった才次郎さんには、我が甲賀一族と同じ血を感じますので、なんとなく親しみを感じるのです。ちと、お聞きしますが、先ほど言われた大原という姓はどちらから出たお名ですかな?」
左門が言い淀むと、遠慮がちに咲が答えた。
「大道寺のお殿様が、才次郎さまとのお別れに際して、大原左門と名乗るようにと名付けられました」
「その大原左門という名は、大道寺様の思いつきですかね?」
「お殿様の思いつきか、心のどこかにその名があったのかは知りませんが、迷いなく大原左門の名をお出しになったのは事実です。きっと、わたしと忠吉さんの出自が大原であることをご存じですから、そこから命名されたのかも知れません」
勘兵衛が左門と孝次郎を見た。
「それにしても、才次郎さんが甲賀の名門の大原と名乗るのも何かのご縁、なぜか、他人とは思えんのだが、この土山宿の用心棒となってこの地に留まってくれませぬか?
孝次郎さんはどう思うかね?」
「わしは、そうまでして才次郎さんに執着しようとは思わぬ」
「しかし、これだけの若者が甲賀に残ってくれたら大きな戦力になると思わんかね?」
「確かにその通りだが、人はそれぞれに自分の道がある。いつかまた才次郎さんがここに足が向いたら戻って来て頂く……それで手を打とうじゃないか」
「孝次郎さんの考えがそれなら仕方がない。残念だが諦めるか」
左門が頭を下げた。
「かたじけのうございます」
志津が一座を見回して、控えめに問い掛けるように告げた。
「そろそろ、お休みになりますか?」
この一言で勘兵衛の腰が浮いた。
「では、わたしは家に帰って湯にでも入って寝るとするか」
勘兵衛が去り際に、さり気なく孝次郎に聞いた。
「孝次郎さん、茶屋の長兵衛の正体は?」
「さあ……?」
「いつ会ってもひょうひょうとして、本性を見せないのが気になってたんだ」
「あの通りの男だよ」
「根来衆を手足のように使えるのも、田島様を狙った武士たちの命を二百両という大金で買い取ったのも凄いが、それで大藩をゆすろうという性根も尋常ではないぞ」
「だから?」
「孝次郎さん! あんたは甲賀党を裏切ってまで長兵衛をかばうのか?」
志津も勘兵衛に続いて夫を攻めた。
「あたしも前から変だと思ってたのよ。あなたは長兵衛さんとだけは私に内緒で会ってるわね?」
佐助が口を出して志津を見た。
「おらは、知ってるだよ」
「なにをだね?」
「長兵衛さんに口止めされてただが、甲賀のためだから言っちゃうだ」
「なにを知ってるの? 隠し立ては許さないよ」
志津の詰問に、佐助が観念したようにしぶしぶ答えた。
「長兵衛さんは、おらに山での走り方、戦い方を教えてくれてただ」
勘兵衛が目を剥いた。
「佐助には、孝次郎さんという立派な師がいるじゃないか?〕 志津も責めた。
「あんたは、一人で山に入って修行してるって言ったでしょ?」
「一人だよ。長兵衛さんの後を追っ掛けるだけって修行だからね」
「どんな?」
「茶屋の裏で会って、長兵衛さんが山に入るのを追うだけだが、長兵衛さんは風のように木々の間を走り抜け、一間も二間も飛び上がって枝から枝を伝って山の中を平地のように走るだが、まだまだ追いつくのは難しいだ」
孝次郎が観念したように呟いた。
「長兵衛さんは、秀吉に滅ぼされた北条家と共に消えた風魔一族の末裔なのだ」
「そんな馬鹿な。風魔は壊滅したはずだぞ?」
「われわれが生きているように、風魔もまた連綿として生き残っている。長兵衛さんは風魔の頭領なのだ」
勘兵衛が呻いた。
「それで読めた。あの長兵衛は、人質にした武士団を手土産に薩摩藩に恩を売り、一族を雇わせるつもりだな?」
「それも、根来衆も含めての仕官になる」
「倒幕の機があればその連中が先駆けを勤めるのか?」
「そのような場合もあろうな」
「孝次郎さんはそれを知っていて、何故に阻止せぬのだ?」
「伊賀も根来も風魔も含めて、甲賀同様に忍びの士は不遇のまま飢えにも耐えての長い年月を、隠忍自重して無為に過ごして来た。ここで、少しでも暮らし向きがよくなれば、お互いに悪いことではないような気がするでな」
「いつか、戦場で敵味方に分かれて殺し合うようになってもか?」
「お庭番で三十石取りの士分に取り立てられたところで、忍びは所詮は野の草だ。どこで踏みつぶされようが文句は言えん。種族を絶やさないことこそ肝心じゃないのか?」
「孝次郎さんはいつから甲賀だけじゃなく、根来や風魔の味方になったのだ?」
「味方でも敵でもない。ただ忍びの道の存続を願っているだけじゃ」
主膳が頷いた。
「太平の世が続くと忍者は不要だが、天下騒乱の兆しある今後はまた活躍の場ができそうじゃな」
勘兵衛が応じた。
「その時こそ甲賀武士の面目をかけての戦いになります」
勘兵衛が去り、左門と主膳は志津と咲が用意した寝具で眠りについた。
甲賀、伊賀、根来……それに加えて、歴史の舞台から消えていた風魔一族までもがこの鈴鹿山系のいずこにか生き長らえていた。しかも、これらの集団がそれぞれ、主膳の言った
「天下騒乱」の時を待っていたのか?
その夜、左門は忍者の群れを相手に剣を振るう夢を見た。黒装束の彼らは切っても切っても不死身のように蘇って左門を襲う。やがて左門は睡魔に襲われた隙を狙われて四方から切り刻まれ、悲鳴を上げながら深い奈落の底に落ちて行った。
