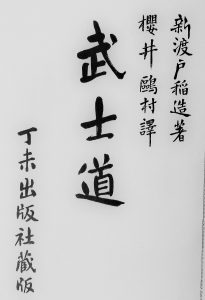清河八郎にみる武士道
花見 正樹
東京都日野市には一風変わった建物があります。
その名は「日野市立新選組のふるさと歴史館」、です。
市内には、日野宿本陣、日野宿交流館、高幡不動尊金剛寺、大昌寺、土方歳三資料館、井上源三郎資料館、佐藤彦五郎新選組資料館など、副長・土方歳三を中心にした新選組ゆかりの数々が遺っていて、1日で史蹟観光を楽しめるのも事実です。ただし、資料館によっては第1第3日曜日の正午から午後6時まで開館というケースがありますから要注意です。
平成26年の夏、暑い日に訪れた「日野市立新選組のふるさと歴史館」で開かれた巡回特別展「新選組誕生と清河八郎」というイベントがありました。
パンフレットを見ると、この年は新選組が結成されて150年目で、新選組の誕生に大きな役割を果たした清河八郎の没後150年、それらを記念して山形県庄内の清河八郎記念館と共催での巡回特別展開催となっています。
私の記憶では日野市立新選組のふるさと歴史館企画コーナーでは、「新選組誕生前夜 ・新選組の“生みの親”清河八郎の軌跡 」とあったように記憶しています。
私は、新選組が好きとか幕府が好きとかではなく、歴史の中に息づく青春群像が好きで時代小説を書いています。
したがって、江川英龍、大原幽学、木村喜毅、清河八郎、土方歳三など、その生きざま死にざまや価値観がたまらなく好きなのです。
天下国家を論じ、国の未来を憂いて多くの志士の心に改革の火種を植え付けて死した清河八郎、この生きざまも好きです。
私は、かなり若い頃に庄内を訊ねて清川神社に詣でて以来、世間の一部からは変節の策士などと誤解されている清川八郎を気の毒に思いました。勤皇攘夷を旗印に、国を憂うる全国の志士達に伝導して歩いた清河八郎の真意を知りたいと思う人は沢山いるはずです。
心ならずも偉業半ばに散った一世一代の快男児の真の姿を太陽の下にさらし、多くの人にその真意を知って頂きたいと思うのです。
上述の「日野市立新選組のふるさと歴史館」での巡回特別展「新選組誕生と清河八郎」が、昔、若い頃に立ち寄ったことのある山形県東田川郡庄内町の清川神社境内にある清川八郎記念館と共催であるのを知ったことで、私は庄内の清川行きを即断しました。
雪が降る季節は、休館になるのを知っていますから、その年の10月下旬、友人(本HP坂本龍馬コーナーの小美濃清明講師)と共に、紅葉真っ盛りで色彩鮮やかな出羽の山々を眺めながらのドライブで、清川神社と清河八郎記念館を訪れました。

また、すぐ近くの齋藤家の菩提寺・金華山歓喜寺にも立ち寄り、清河八郎とお蓮さん、齋藤家のお墓に詣でて手を合わせ、ご一族のご冥福とこれからの皆様のご繁栄を祈りました。
ところが驚いたのは、斎藤家の広い墓地敷地内に、戊辰戦争で戦死した藩兵や民兵の墓、天保飢饉の際に齋藤家の蔵米を運び出して処分を受けたとされる農民を悼んで齋藤家が建てた「義民(15名)之慰霊碑」などがあるのです。これを見ただけで、私は目頭が熱くなり裕福だった齋藤家の温情と地域住民にいかに気を遣ったかが理解できたました。

歓喜寺の創建は、天正7年(1579)に旨光上人が開山したとも聞きますが、境内は2400㎡と広く、本堂、庫裏、開山堂、位牌堂などの諸堂を配置したいかにも歴史のある古刹という感じで住職さんの穏やかなお顔を拝見しただけで、戊辰戦争での庄内藩基地になった歓喜寺で西軍を撃破して清川から追い落としたとの言い伝えも神仏の力と代々のご住職が持つ仏力の影響もあるような気がしました。
幕末にその名を残した清河八郎は天保元年(1830)10月10日、庄内藩領の国田川郡清川村の裕福な酒造業で郷士の齋藤治兵衛と亀代夫妻の長男として生まれました。幼名は元司(もとじ)名は正明です。
幼児期から天賦の才を発揮して周囲を驚かしたり、腕白坊主ぶりで困らせることもありましたが、14歳から論語や孟子、易経や詩経を学び、17歳から剣術を学んで文武両道への道を歩み始めます。
その年、元司の人生を変える出会いがあります。東北巡遊中だった30歳の藤本鉄石(後の天誅組総裁)が齋藤家を訪れたのです。
清川に滞在した鉄石の教えで江戸遊学を思い立った元司は、弘化4年(1847)に18歳で江戸に出て、江戸古学派の東條一堂に師事して頭角を現し、東条一堂塾の三傑に数えられるようになり、4年後の嘉永4年(1851)には塾頭に推挙されます。
さらに八郎はその年に北辰一刀流・千葉周作の玄武館に入門し、翌年には初目録、安政5年(1858)に中目録、万延元年(1860)には早くも北辰一刀流兵法免許を得て、剣の道でも一流になります。
学問も、それと同時並行で、昌平坂学問所、安積艮斎(あさかごんさい)塾、昌平坂学問所を経て、安政元年(1854)には、江戸神田三河町で「清河塾」を開きます。弱冠25歳、この時、名を改め、当初は故郷の名をとって清川八郎と名乗りますが、すぐに日本三大急流の最上川から大河の意をとって「清河八郎」とします。
安政4年(1857)に八郎は、火事で失った清河塾を、駿河台淡路坂に再開します。
この頃、千葉道場で知り合った幕臣で尊皇攘夷論者の山岡鉄太郎とその義兄・高橋泥舟とも親しく交わります。
徐々にまた門弟も集まりますが、またしても火事で塾の建物を失います。
それでも八郎はめげません。
安政6年(1859)、神田お玉が池に3度目の清河塾を開きます。
その清河八郎は北辰一刀流の免許皆伝で、剣術も教えましたから、「清河塾」は江戸で初めての文武両道の道場となり、清河八郎は文武兼備の英士として名を知られてゆきます。
清河八郎が憂国の志士として活動し始めるのは、万延元年(1860)に大老・井伊直弼が、江戸城桜田門外で水戸浪士らの襲撃を受けて惨殺された事件に触発されてからと思われます。
私は、清河八郎は少年時代から易経を学んでいることから、先を読むことも、ある程度は予知能力をも身につけていたと考えています。
八郎は、桜田門外事件の1ヶ月前、国難に対処するには勤皇攘夷を軸に、虎の尾を踏む危険をも省みず、と「虎尾の会」を結成します。
連判状に名を連ねるのは、山岡鉄太郎、松岡万、伊牟田尚平、樋渡八兵衛、神田橋直助、益満休之助、美玉三平、安積五郎、池田徳太郎、村上俊五郎、石坂周造、北有馬太郎、西川練造、桜山五郎、笠井伊蔵・・・八郎を入れて16名、ここには坂本龍馬はいません。巷間には 坂本龍馬もこの会に連座している、という文章を見ますが、私はまだ確認していません。
八郎と龍馬が同じ巻紙に名を連ねているのは、北辰一刀流・玄武館での稽古試合名簿で見ました。
「虎尾の会」の諸氏は直ちに行動に移すと言い、血気盛んですが、八郎は時期尚早と必死に皆を抑え、このままでは幕府の密偵に探られるから一時「虎尾の会」を解散することも考えます。
そんな矢先、その年の暮れに、益満、伊牟田、樋渡らが、米国ハリスの通訳ヒュースケンを暗殺してしまいます。
役人の探索で清河塾が疑われ、八郎は捕吏に監視され、翌文久元年(1861)、幕府の罠にはまることになります。
運命の5月20日、水戸藩士主宰の書画展の帰路、その前日に逮捕状が出ていたことで捕吏に囲まれます。一人を切り捨ててその場は逃れますが、八郎は追われる身となり、虎尾の会同志数人や妻のお蓮、弟の熊三郎らが連坐したとして捕われて投獄されてしまいます。
ここから八郎の逃亡生活が始まると同時に、勤皇攘夷から討幕の方向へと舵を切ります。
京の公卿・中山家に接近し、九州遊説で真木和泉や川上彦斎、宮部鼎蔵や平野国臣らとも親しくなり今後の策について話し合っています。
その結果、文久2年(1862)の薩摩藩主・島津久光の上洛まで待ち、久光が倒幕の狼煙を挙げたのを見届けて、全国各地の尊攘派志士に呼びかけ、京都で一挙に挙兵して倒幕に走ることで結論が出ます。
だが、この時はまだ肝心の島津久光の本心が、自分も幕閣の中枢に入っての公武合体であることを誰も見抜いていませんでした。
その後、京都伏見の寺田屋に集結した過激な薩摩藩士を、久光が派遣した説得士との間で上意討ちの乱闘という悲劇になり、清河八郎が画策した薩摩藩を柱にした討幕への戦いは不発に終わりました。
孝明天皇も公家・岩倉具視を通じての公武合体に心を動かし、勅旨が江戸に下って将軍家茂の上洛と公武一和の機運が盛り上がります。
その機を八郎は逃がしませんでした。
密かに江戸に戻った八郎は、将軍家茂が上洛するには、屈強な護衛団を必要としている情報を入手して、すかさず策を練り、仲間の山岡鉄太郎を通じて幕府政事総裁の松平春嶽(しゅんがく)に「急務三策」と題する腕の立つ浪士組募集の建白書を提出します。
これは、攘夷の断行、浪士組参加者の大赦免罪、文武に秀れた剣士の重用、この3項目です。
幕府は、この八郎の建白書に、渡りに舟とばかりに飛びつきます。これで、将軍上洛の護衛が万全になります。
この浪士組編成によって、不逞浪士の懐柔策にもなり、獄中の志士や同志の大赦、八郎自身も自由の身になれ、さらに今後の同士集めにもなる一石4鳥の妙策となります。
その浪士組募集が成る経緯は省略しますが、浪士組一行が京都に到着して壬生村へ入った夜、八郎は浪士組全員を新徳寺の本堂へ集め、「われらの本分は尊皇攘夷にある。幕府ではなく天皇と日本のために立ち上がり、外国勢力を打ち払う!」と尊皇攘夷論を説きます。
突然の話に驚いた浪士たちは困惑して何も言えません。そこで八郎はすでに用意してあった血判状を広げ、各人の署名と血判を集めましたが、たった一人、虎尾の会の同志・池田徳太郎だけが署名せず、八郎の早業を諫めています。
八郎は翌日、代理人を立てて京都御所の学習院へ血判状を提出し、朝廷側も揉めたようですが目出度く受理され、浪士組宛ての勅諚を賜ります。これには、血判を捺した当の浪士組全員が感激して涙を流す者もいます。なにしろ、身分の低い浪士ごときが天皇のお言葉を賜るなどは前代未聞の出来事で、夢の中でもあり得ないことです。
その頃、江戸では、横浜で起きた薩摩藩士が藩主の行列を横切った英国人を殺害した生麦事件の賠償問題が難航していました。
英国側は、島津久光を引き渡す、こちらが提示した賠償金を差し出す、このいずれかが実行されない場合は軍艦を差し向け武力に訴えるが戦う用意は? という強硬なもので、幕府の外国奉行は判断に窮して、上洛中の将軍の決裁を求めて早駕篭で使者を二条城に送ります。
これを伝え聞いた八郎は、攘夷の実行こそ我らが目的と喜び勇み、朝廷に2回目の破約攘夷によって生麦事件の賠償金拒絶による開戦の建白書を上奏します。これは、外国嫌いの孝明天皇にとって有無はありません。直ちに勅諚が下ります。
その勅諚を手にした八郎は、江戸へ戻る旨を山岡鉄太郎に伝え、浪士組全員に報告するために集会を開きました。
この八郎の突然の江戸への帰還に反対して京都に残留したのは、芹沢鴨、近藤勇ら24名となります。
これを知った浪士組引率の責任者・鵜殿鳩翁は驚きながらも芹沢・近藤の意見に耳を傾け、京都守護職で会津藩主である松平容保(かたもり)公の承諾を得て、浪士残留組は会津藩預りということになって壬生浪士組から新撰組、さらに新選組となっていきます。
江戸に戻った清河八郎の評判は高く、浪士をまとめて天皇からの勅諚を得たという噂は世に広まっていて、浪士組参加希望者は門前列を成す勢いですが、それを幕府が黙って見逃しているはずはありません。
しかし、浪士組は攘夷戦争に備えて東帰、との勅諚がある以上、手を出せません。
かといって、幕府は、朝廷の命ずる破約攘夷実行で英国と戦争するわけにもいきません。
江戸期間後の2ケ月近くを無為に過ごした八郎は、浪士組だけでの横浜外人居留区襲撃を画策し始めます。
その間にも、浪士組に入隊希望の剣士監視が続々と参集しますので、八郎傘下の戦力は数百人となって膨れ上がっていて、すでに幕府でも制御できない状態で、清河八郎の存在は、幕府にとって危険人物となってしまったのです。
すでに身内は囚われの身となり、風の便りでは、お蓮も獄中で病に伏して逝き、母も厳しい折檻で痛ましい姿とか。
八郎は自分のために多くの犠牲者を出したことを悔いますが、もう後戻りは出来ません。
幕府は、清河八郎に刺客を送ることになります。
こうして運命の四月十三日の朝がやってきました。
八郎は少し風邪気味だったとも伝えられています。
若くして易占に親しんだ八郎は、すでに死期を悟っていたようです。

多分、この朝易を立てたら現れる卦は「震為雷」、八郎の好んで用いた家紋です。
この卦は、雷の重なりで易卦のなかでも極めて激しくい卦の一つです。
「稲妻が走り雷鳴が轟き天下争乱の中で泰然と我が道を往く」
もう一つの解釈は、この卦が「雷鳴千里を轟かす」の易意から考えました。
「天下に名を轟かす偉業を為す」
思えば、齋藤治平衛豪寿(ひでとし)の長男として元司が産声を上げた時、雷鳴が轟き稲妻が走ったといいます。
一代の快男児の幕開けは激しく、幕を閉じるのは音もなく静かなのかも知れません。
この日は、郷里の先輩でもある上山藩・金子与三郎邸に招かれていました。
八郎は銭場で身を清めて、世話になっている山岡家の隣家の高橋泥舟邸に立ち寄ります。
泥舟がすぐ八郎の顔色を見て、外出をしないように進言します。
曖昧に返事をした八郎は、筆立てを出して、泥舟の妻のお澪(みお)に告げます。
「白扇がありましたら二本ほど所望します」
お澪が手渡す白扇を広げると八郎が墨痕鮮やかにさらさらと歌を書きます。
魁(さきが)けてまたさきがけん死出の山 迷いはせまじ皇(すめらぎ)の道
くだけてもまたくだけても寄る披は 岩かどをしも打ちくだかん
この歌を見た泥舟が、辞世の歌と知って驚き、強く足止めをします。
「今日は絶対に家を出てはいかん」
妻にも見張りを言いつけて、泥州は登城の途につきます。
そのうち、山岡の妻で泥舟の妹のお英(ふさ)と、その妹のお桂が朝の挨拶と称してお喋りにやって来ます。
聞くと、鉄太郎が、銭湯帰りの八郎が高橋家に寄るはずだから、行って茶でも飲んで、八郎を外出させるな、と言ったそうです。
鉄太郎も登情前に、何となく八郎の異変に気付いていたのです。
八郎はそれには触れず、お澪に再び白扇を二本求め、ただちに筆をとります。
「君はただ尽くしませ臣(おみ)の道 妹(いも)は外(ほか)なく君を守らむ」
同じ歌を白扇に書き、お英とお桂に手渡して、出された茶を飲んでいると、山岡邸の門前に金子与三郎の迎え駕篭が来たようです。
「では、行って来ます」
八郎は、引き留める女達の手を振り払って山岡邸に戻り、支度して家を出ます。
服装は、黒羽二重の紋付き羽織に仙台平の鼠色縦縞袴に黒旅に草履です。
腰の愛刀は、備前三原正家で刀身に「がんまく」の字があるので「四字がんまく」と呼ばれる業物です。
麻布の上山藩邸で金子ら数人に歓待された八郎は、勧められるままによく食べよく飲みよく喋っりました。
八郎は夕方になって藩邸を辞し、駕篭を断って、夕風に酔いを醒ましながら麻布一ノ橋を渡り始めました。
ここまでで記述を止めます。
私は、佐々木只三郎が1対1で真剣勝負を挑んでくれたら、八郎も堂々と受けて立ち、歴史に残る好勝負になったと思います。たとえ、上から暗殺を命じられたとしても武士の情けはあって然るべきかと思います。
「清河八郎は、すごい人だった。このまま生きてくれたら国は大きく変わったのに・・・」
誰もがこの怪物とも言われた清河八郎を大人物と認めて一目置いていたのです。
清河八郎の目指した「回天報国」、世を変えて国に報いるために一命を賭した生きざまこそ武士道の本筋であると信じます。